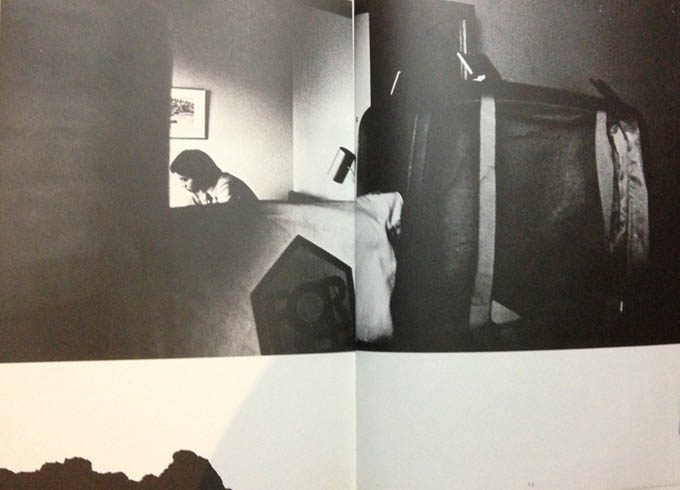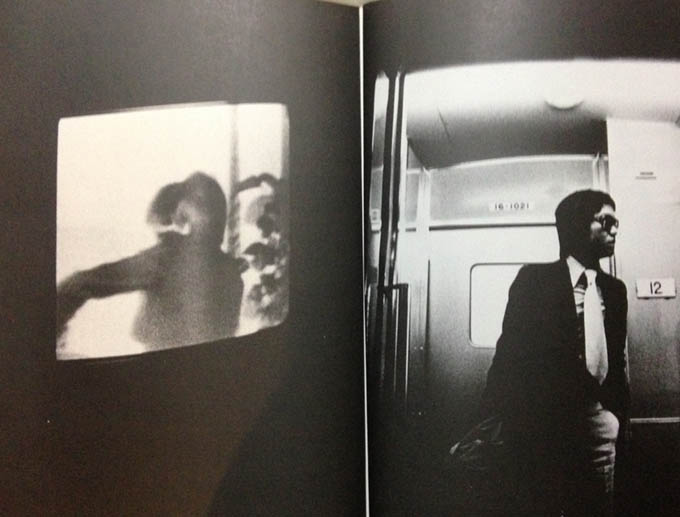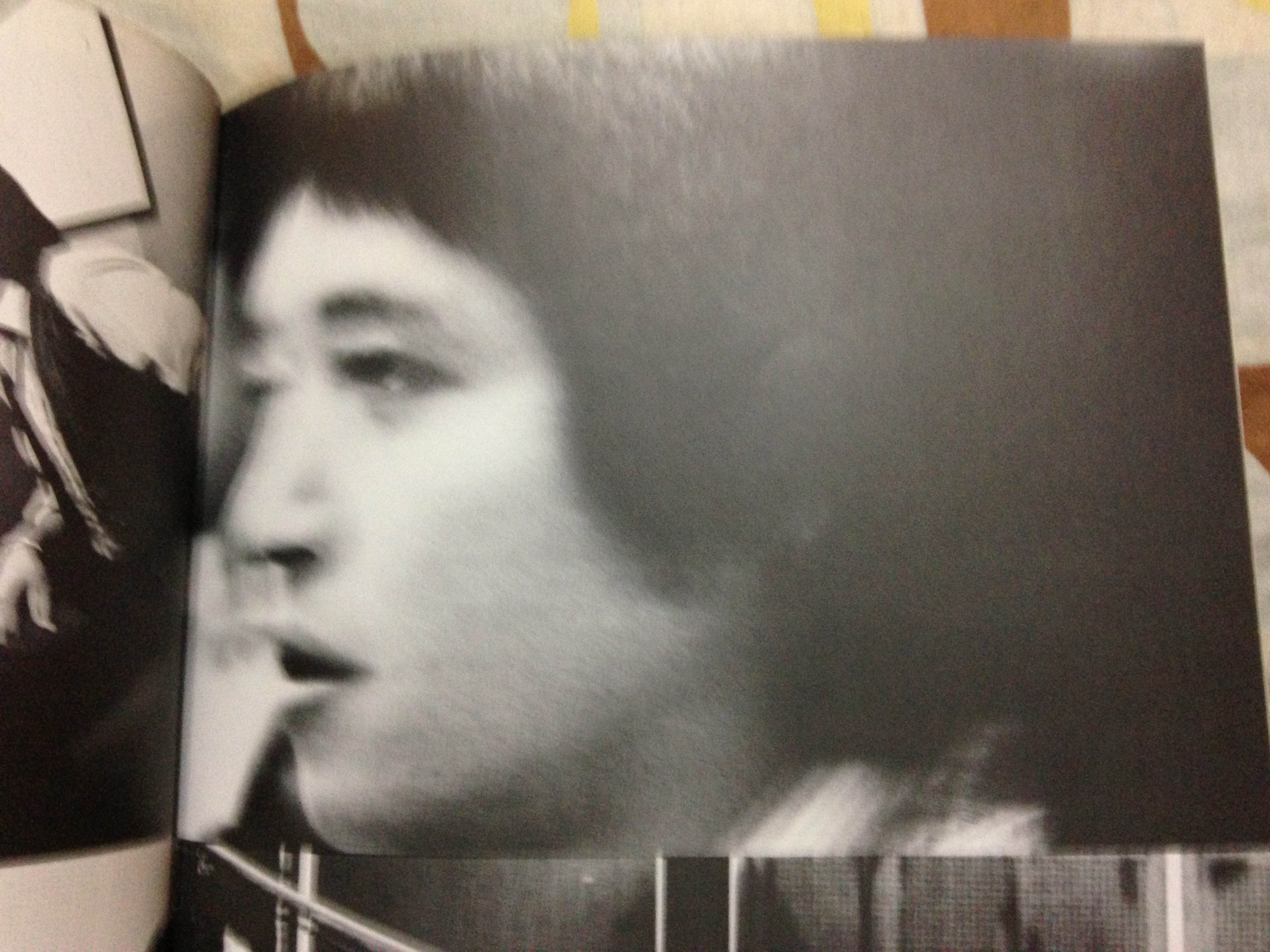プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)
- TEXT:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- Special
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 75-2
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- special 2
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- special 3
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- special 4
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
一月中旬、北海道でロケをしていた。ロケ地は雪降る元炭鉱町。札幌市内からの行きは車だったが帰りは車組と別れ車中からの雪原を撮るためにジーゼル車に乗った。途中乗り継いだ駅のホームの行き先案内に苫小牧の地名を見たとき、突然、「苫小牧発仙台行きフェリー、あの爺さんときたらわざわざ見送ってくれたよ」と、吉田拓郎の『落陽』の一節が雪景色に鳴り響いた。北国の幻聴だ。
その数日後、仕事仲間と地元駅前のカラオケ・スナックに行くと、いつもは満席なのだが、その日は陽水ファンの常連客とはじめて見る客のふたりだけ、ともに中年の男性。陽水ファンは『リバーサイド・ホテル』と『ワインレッドの心』二曲絶唱し、帰って行った。
ぼくらも歌い興じていると、残った客が「拓郎、歌おう!」と叫ぶ。「じゃ、歌おう」とぼくが『夏休み』を歌った。その客も何曲か拓郎を歌ったが、「流れる雲を追いかけながら----」と『明日に向かって走れ』を歌い出すと、途中、嗚咽して手を目に当てている。あとに歌がつづかない。明らかに感極まって泣いている。
「つま恋で拓郎が最後に、この曲を歌ったんだ」とうめいたあと、「拓郎、死ぬなよ!」と叫ぶ。拓郎は癌に冒されたが、再起したはずだ。それでも活動休止に追い込まれ、また再起したはずだ。
「あの客、本気で泣いてますよ」
と連れが耳打ちする。
拓郎の本を4冊編集した。エッセイ集と詩集と写真集2冊。一冊はこのプロフィールでも触れた1975年のつま恋コンサートのドキュメント。もう一冊はアルバム『大いなる人』発売直後に制作した同タイトル本。
そのとき拓郎はフォーライフ・レコードの社長に就任していた。アーティスト兼社長として全国主要都市をプロモーションで回る拓郎に密着し、長濱治が写真を撮り、ぼくがインタビューをしノン・フィクションのテキストを書いた。都内での特撮も行なった。判型はビィジュアル本のサイズになっているが、全体の半分は読み物だ。アルバム『大いなる人』の楽譜もついている。
長濱治の60年代調といってもいい粒子が荒れコントラストの強い独特の白黒写真はブルーズを感じさせ、いまも新鮮である。長濱治はニューオリンズからシカゴまでブルーズの足跡を追った写真集をつくっている。ニューヨークのヘルズエンジェルズのドキュメント写真で一躍名をなした、という意味ではゴンゾ系だ。
長濱さんとは去年二度、黒人ミュージシャンやジャズ・バンドのライブ会場で顔を合わせた。何年か前にはビートたけしや高倉健が登場する男の顔の写真集でぼくの顔も撮ってくれた。
年齢は十歳ほど上だ。つきあいは1970年から。そのころからよく仕事をした。助手についていたのが三浦憲治と若松プロ出身のガイラだった。長濱組は不良の匂いがした。返還前の沖縄の娼館でドロドロの撮影をしていた。
長濱さんにはよくミュージシャンを撮ってもらった。泉谷シゲルや矢沢永吉だ。その流れもあって吉田拓郎を撮ってもらったのだろう。このとき拓郎と長濱さんは初対面だった。スナップにしかならないようなシチュエーションで、長濱さんは拓郎を撮った。それでも作風があるから劇的な印象を受ける。
拓郎とのインタビューを読み返す。拓郎には何度もインタビューしているが、この人は自分のことを包み隠さず語る。飾ることなく語る。心情を吐露する。お父さんは確か物を書く仕事についていたはずだ。語りがうまい。
1977年11月14日、東京ー名古屋間の新幹線車中でインタビューしている。
矢沢永吉は広島から夜汽車に乗って上京したが、拓郎は新幹線できたのではないか。拓郎は新幹線が似合う。
拓郎と並んで席に座っている。ぼくが話しかける。
ーー岡林信康とか加川良、北山修とかフォークの神様やスターって言ってたわけだけど、彼らはある時期スターであることと決別した。吉田拓郎はながいですよね。現役のままトップをはしってる。
「やっぱり彼らは潔よかったのかな。俺は潔わるいのかもしれない。ただ、岡林とか加川とかは似たような奴があとから出てきた。そうなると、より新しい方向へ進むか、あるいはアッサリとケツをまくっちゃうかさ、方法があるだろ。俺の場合は幸か不幸か出てこなかったんだ。俺のパターンで凄い奴がでてきてたら、そういう方法をとったかもしれない」
ーーチャンピォン・ボクサーがリングで挑戦者を迎えて闘いつづけ人生を燃焼したいと願うけど、誰も相手がいない、そんな空しさ感じる?
「たとえばボクシングのチャンピオンでロベルト・デュランっていう奴がいるよね。凄いKO率でさ。向かうところ敵なしだよ。ぜんぶKO勝ちさ。つぎからつぎと挑戦者倒して、なおかつ常に自分を鍛えてる。俺は自分を鍛えてなんかいない。そこが違う。自分の立場守るために、そのボクサーは鍛えつづける、そこが凄いわけよ。そういうの、俺はない。いつもダラダラしてるわけだから。それでも俺が倒されないというのは、結局、ボクシングでいったら、俺のクラスの選手がもういないんじゃないかって気がする。つまり、俺のクラスは排除された。新しいクラスを俺がつくったんだけど、もうそのクラスは協会に登録されてない」
ーー確かにいまの音楽はポップだな。軽い。
「違うウエイトだから闘いになんない」
ーーそうするとセコンドにまわっていまの音楽の主流のクラスのチャンピオンを育てるしかない。
「原田真二はそれだな。で、彼と俺がリングで戦うことはないわけさ。あいつは俺を超えるだろうとは思う。それが具体的にどういう方法でかというとね、激しい戦いなんてない。ぼくはちがうんですよ、とかわす。俺とははなからちがう、と。ウエイトがちがうから俺に挑戦状は叩きつけないだろうという気がする」
ーー「吉田拓郎の時代」はチャンピオンのまま終わりを迎える?
「どこかの雑誌社の取材で言ったんだけどさ、『子供に自分のやってきたことを引き継がせたいか?』って聞かれてさ、俺はそんな気持ちまったくないと答えたんだよ。吉田家の血はね、親父が死んで、長男と俺が引き継いでるんだけど、俺で根絶やしにしていいって感じる。吉田の血は俺一代でおしまい。たとえばWBAが決めたクラスは吉田拓郎がチャンピオンになって終わり。次からは別のクラスが開設されると。あらゆる意味から言っても、俺みたいのは俺一代で終わりだろうって気がするな」
話しは拓郎の音楽的ルーツへと遡っていく。
「俺、アマチュアのころさ、米軍のキャンプなんかに行ってさ、よかったわけよ、感動がなんとも言えずさ。白人の音楽やると黒人は出て行く。黒人の音楽やると白人が帰って行く。ハッキリ別れててさ。それを一喜一憂しながらやる満足感ってたまんなかったわけよ。音楽って凄いと。こんなに説得力のあるもんだと思わなかったからね。人種によって雑音になったり快感になったり、こんな凄い刺激はない。プロになってからも、そのころの感じって捨てがたいんだよ。いまでもそのころのテープ持ってるんだけど、いま聞くとヘタはヘタくそなりに生き生きしてんだよ。オーティス・レディングなんかさ、コピーなんだよ、でも歌いながら泣きそうになってるわけよ。陶酔しきって歌が身にしみちゃってるんだ。そういうの思い起こしたいし、思い起こす度にそこに戻ってリズム&ブルース歌いたくなる」
ーーもっと素直に曲を作りたいと。『明日に向かって走れ』はきつかったのかな?
「あのときはさ、別れがあったわけじゃない。それがテーマになってるよ。無理やり自分を歌で奮起させてざ。明日に向かって走らせようと鞭うってね。闘争本能を駆り立てて。それでやってると死にそうな気がした。だから、あのレコードはいいと思う反面、きつい。重くて、息が抜けない」
ーー『大いなる人』は、どう?
「刹那の気持ちの昂まりでやってきたものを、一日の気持ちの流れにした感じだな」
芝浦創業90年最古の居酒屋・大平屋の旦那は若いころ拓郎のファンだったという。女将さんはフレディ・マーキュリーを熱愛していたんだけど、旦那は拓郎ファン。
ぼくは拓郎のレコードもCDも一枚ももってないが、『ライブ73'』というアルバムは日本のロックの頂点を極めていると感じた。カラオケで歌うのはいつも『旅の宿』だ。短い歌なのに酒、湯、肌が濃厚に匂う。
吉田拓郎と矢沢永吉。ともに広島。イニシアルはともにY。
スーパースターのイニシアルはYが多い。
吉田拓郎、矢沢永吉、陽水、ユーミン、山下達郎、YMO------