マシンガン・ケリーの伝説
by Hiroshi Morinaga
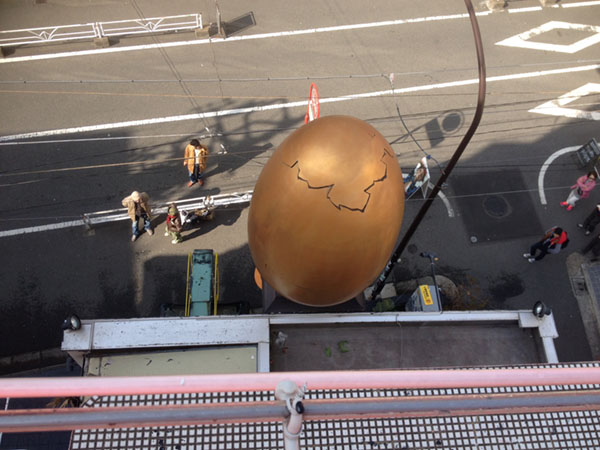
1 「陽のあるうちにやっつけよう」
陽のあるうちにやっつけるしかない。時間は、前日、電話で12時と決まった。「で、用意するものは?」
ケリーに訊く。
「シナベニア、二枚」。他、幾つかの注文を受ける。
ついに、その日がやってくる。祈るは、天気のみ。
それはDVD『DOQROがぼくの夢をみる前に』のための特別なアート・パフォーマンスだった。
それはまた厳粛な儀式でもあった。
約束の時間の30分前にキャット・ストリート・サウス、ピンク・ドラゴン・ビル(以下PD)に着く。すでにケリーは、快晴の空の下、PD前の路上に突っ立っていた。アーミーグリーンのツナギにキャップ。助手の若者・會田を連れている。
屋上ではDVDの監督の大介がベニアを打ちつけボードを工作している。
「何、描きます?」、路上で訊く。
「ジェームス・ディーン」
とケリーは言って、バックから一枚のコピーを取り出す。
「これ。青学裏の〈TWIST NO1〉の壁面に描いた絵だよ」
「やっぱり、あそこの絵はケリーが描いてたんだ!?」
「そう」
「マリリン・モンローも描いた?」
「描いた。モンローがものすごくいやらしくコカコーラを咥えてる絵ね」
「あれは、衝撃的だった!」

1970年、それがはじめて見たケリーの壁画だった。いまも、その壁は残る。もちろんケリーの絵はないが、いつも、その壁一面にはまるでそれが伝統のように誰かの手によってグラフィティーが描かれている。ケリーがそこに最初に描いたのだ。それが、東京初のグラフィティーだった。まちがいない。
場所は、青学の真裏、六本木通り沿い。青山トンネルの渋谷寄り。壁面は長い。そのなかに「青山のケツの穴」のように、一軒のロックンロール・スナックがあった。山崎眞行が伴晋作と雇われで開いた〈TWIST NO1〉だった。
そのころ山崎は新宿にも〈怪人二十面相〉という店を持ち、ケリーはすでに店内の壁面や看板、マッチの絵を描いていた。山崎の商売にケリーの絵は欠かせないものになっていた。
「おれは、その頃から原色でしか描かない」
路上でケリーは言う。昨日、アンディ・ウォーホル展の内覧会をのぞき、ケリーのテンションは上昇している。
用意ができましたと、大介から連絡がはいる。みんなでブルックリンの古びた倉庫の非常階段のような階段へ向かう。いよいよ、出撃だ。儀式のはじまりだ!
2013年3月24日、午後1時、屋上のペントハウスの住人にしてPDのオーナーであった山崎は愛犬のクロと、その階段を降り、散歩に出て、桜吹雪く路上で倒れ帰らぬ人となった。翌日帰ってきたのは亡骸だった。下りではあったが、それはまさに「天国への階段」だった。
バルコニーに出る。ベニア二枚分のボードが側面に立てかけられてある。大介はライブ・ベインティングを俯瞰で記録するためにカメラを住居の屋上にあがりセットしている。
ケリーはバルコニーの片隅に道具をひろげる。ペンキは赤、黄、青、黒。筆は、意外と細い。平筆と言うらしい。ペンキは水性なので、筆洗いの器。あとは青のチョーク。そんなもんだ。


さっそく、ボード全面を白く塗る。ぬけるような青空。その青もはやケリーがこれから描こうとする絵の背景に思えてくる。
突然、奇妙な感覚に襲われる。あまりに突然、山崎が消えてしまったので、すでに半年たつというのにまだ実感がない。カーテンがしめられたままの住居のドアがあき、寝起きの山崎が姿を見せ、「あれ、みんな、何やってんの?」とうれしそうな笑顔を見せる気がする。白日夢を見ている。

下塗りが完成する。ここで、一服。「なんか、食べようか?」、ケリーが言う。「じゃ、ものすごくうまいハンバーガー、出前してもらいます」。〈ゴールデン・ブラウン〉のノブりんに電話注文する。
無性にバーガーが食べたくなっていた。PDの二階に、1983年〈ドラゴン・カフェ〉もオープンした。そこでは山崎がロスでレシピを仕込んできた照り焼きバーガーが食えた。〈ドラゴン・カフェ〉の特注ドアは山崎の住居のドアになり、カウンター内のアール・デコのステンレス製の棚はオーディオ装置が内蔵され、やはり自宅の神殿になった。そのドアを見ている。
夏、山崎を偲ぶ身内の飲み会の席でケリーと雑談しているうちに、ふと、閃きがおりてきた。追悼ドキュメンタリーのために、ケリーにライブ・ペインティングをしてもらう。言うと、「いいよ」、即答だった。
かつての朋友が山崎の霊魂に山崎が生涯、一途に愛した50sのアイコンをライブで捧ぐ。このアイデアに自分は興奮した。
山崎は少年時代、絵を好きで描いていた。その生涯でつくった店も服も小物もすべて山崎にとっては絵だった。そのイメージの源にあったのは、生まれ故郷の北海道赤平の映画館で見た50年代のアメリカ映画、日活映画だった。
山崎が上京し新宿で初めて会った絵描きがケリーだった。山崎は店の壁をケリーの描く絵で埋めつくした。その瞬間、のちの〈クリームソーダ〉のスタイルが誕生した。それは内装やデザインではなく、チープでインパクトがある、まさにロックンロールの小宇宙だった。
山崎とケリー。まだ学生運動、フーテン、アングラ、ハプニングで混沌とし、北野武が歌舞伎町のジャズ喫茶のウエイターだったころの魔都・新宿の片隅で、ふたりは運命的な出会いを果たしたのだ。
そのケリーの絵を、ライブで山崎に捧ぐ。
「店で壁に絵を描くときって、店が終わってからなんだよ。夜中に終わって、翌日もう昼から営業だから、描く時間ない。だから、顔が似てようが、体のバランスがおかしかろうが、そんなの気にしてらんない。それがいつの間にか、おれのスタイルになっちゃったんだ」
と思い出しながら、ケリーは青いチョークを手に下書きに入る。
左手にはジェームス・ディーンのコピーをおさめた透明ファイル。ファイルにはコピーを八等分するラインがひかれ、それで当たりをとる。右手でボードにアウト・ラインをひいていく。
ハンバーガーを目黒の店から配達にきたノブりんは、余程ケリーのライブ・ペインティングに興味を示したか、店には戻らず、見物している。
70年代の原宿では、町は田舎のように長閑かで、店や事務所に知人を訪ねると、そのまま一日中雑談にふける自由な空気があった。時間にも金にも追われていなかった。まして流行にも。原宿生まれ育ちのノブりんはバルコニーでそんな空気にひたっている。他にも、一階の売り場や地下の事務所から店員や本多さん、クロを連れた西尾、ミッキーらが見学にくる。
下書きがおわり、駆けつけてきたリサ・バンドのボーカルのリサも助手に加わり、色を塗っていく。ケリーはリサ・バンドのドラマーでバン・マスだ。年長者のケリーに若者たち。一心に色を塗っている。絵を描くこと、バンドをやること、それが68歳になるケリーが到達した生き甲斐に思える。
撮影のためとはいえ、そこに流れている空気は、そのとき、世界で一番、自由さに満ちている。青空のした、すべてが、創作の解放感に満ちている。
「これが、おれのアメリカの色なんだ。青、赤、黄。スーパーマンの色だよ。アメリカの田舎を車で旅すると、ビルボードとかガソリン・スタンドとかスーパーとか、目に入るのは、この三色だろ」
という三色がベタ塗りされていく。それはスリー・コードのロックンロールと同じだ。そこで、肝心なのはベタ塗りだ。
山崎は、その魔法に気づいていた。山崎は言っていた。日本のペンキ屋は、建材の素地を活かすためにペンキを薄く塗る。でも、自分の店では厚く塗った。そうすると、ペンキの刺激的な匂いに惹かれて、客がはいってくる。
山崎は高校時代、美術部にいた。〈クリームソーダ〉の本多は同級生だった。美術の時間、絵を描くとき、山崎はみんなにチョークを粉々に砕かせ、それを水彩絵の具に混ぜさせ描かせた。そうすると、表面がゴテゴテ、油絵のようになる。そんな誰にも思いつかないことをした、と本多は言う。
配色が完了する。まだ、絵は見えない。幻のようだ。か、遠い、おぼろげな記憶のようだ。ケリーは陽射しに目を細め、幻を見ている。ハンバーガーに食らいついている。
ケリーは膨大な数のロックンロール画を壁やレコード・ジャケットらに描いてきた。なのに他のイラストレーターのように業界で脚光を浴びたことはない。ケリーは、そのことを自覚している。最近、マクドナルドの広告が、どうみてもケリーの絵にしか見えない。しかし、よく目を凝らせば、色の使い方がロックンロールに欠ける。不良性がない。ヤワだ。
イラストレーターの描く絵はアトリエで机に向かって描く姿が見えるが、ケリーはバスキュアのように路上や深夜の店やベニアに描く姿しか想像できない。その意味では、異端の画家だ。
これと同じことが〈クリームソーダ〉にも言える。山崎は幾軒ものショップ、膨大な数の服をつくり、その角ドクロ・ブランドは一世を風靡したが、アパレル業界ではずっと異端のままだった。
だけどケリーも〈クリームソーダ〉も、どんなイラストレーター、ブランドよりも熱烈なファンをもっている。
最近、ケリーはマックショウのアート・ワークを依頼され、その絵はCDジャケットだけでなく全国をめぐる熱狂的ツアーのステージにも垂れ幕で飾られている。ケリー・ファンのショップはケリーに壁画を描いてもらい、絵をデザインした服や小物を制作し販売する。熱狂的ファンは個人的に革ジャンに絵を依頼する。
決してコマーシャルな仕事ではないが、その45年にもなろうとする画業に終わりはこない。カルト画家としての人気はむしろ高まっている。
まさに、これこそがロックンロールだ!
しかし、ケリーは山崎と、どのようにして出会ったのか?
その数ヶ月後、ケリーと渋谷のカフェで会い、話しを聞いていた。
遠い日の、それは思い出。しかし決してセピア色にならない、原色がギラギラぬめる、いまにもナイフが飛び出しそうな、それはストリートに踊る髑髏たちの饗宴! スペードのカードが闇に舞う。一気に半世紀を逆走し、ケリーはまだ若僧。ヤング・ケリーの物語。

