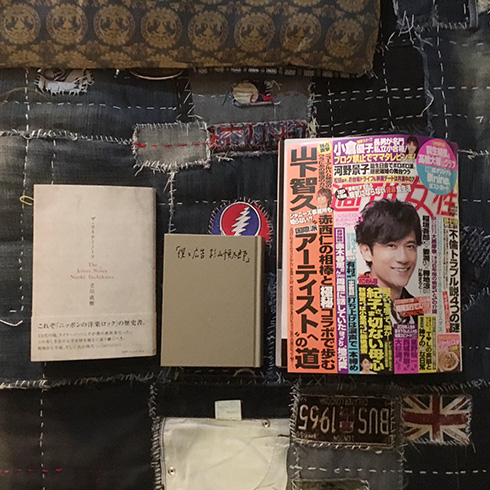プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)
- TEXT:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- Special
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 75-2
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- special 2
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- special 3
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- special 4
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
寄せる
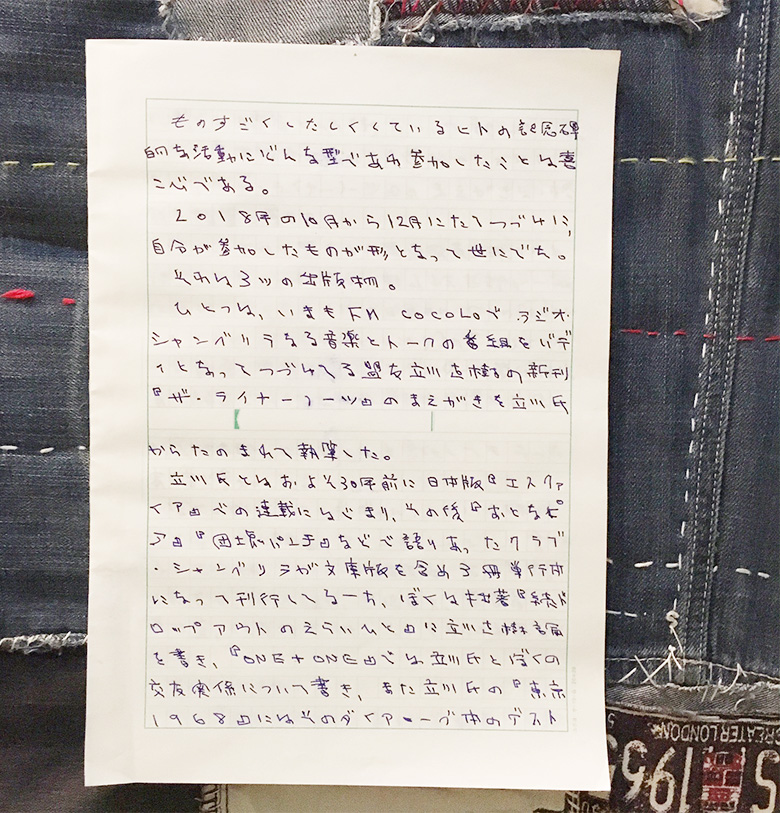
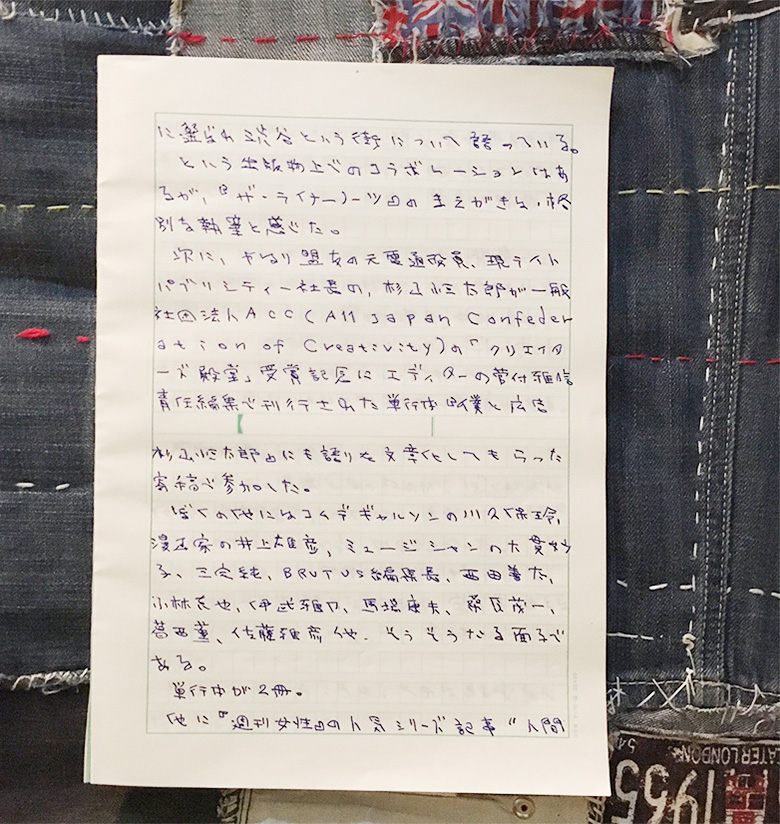
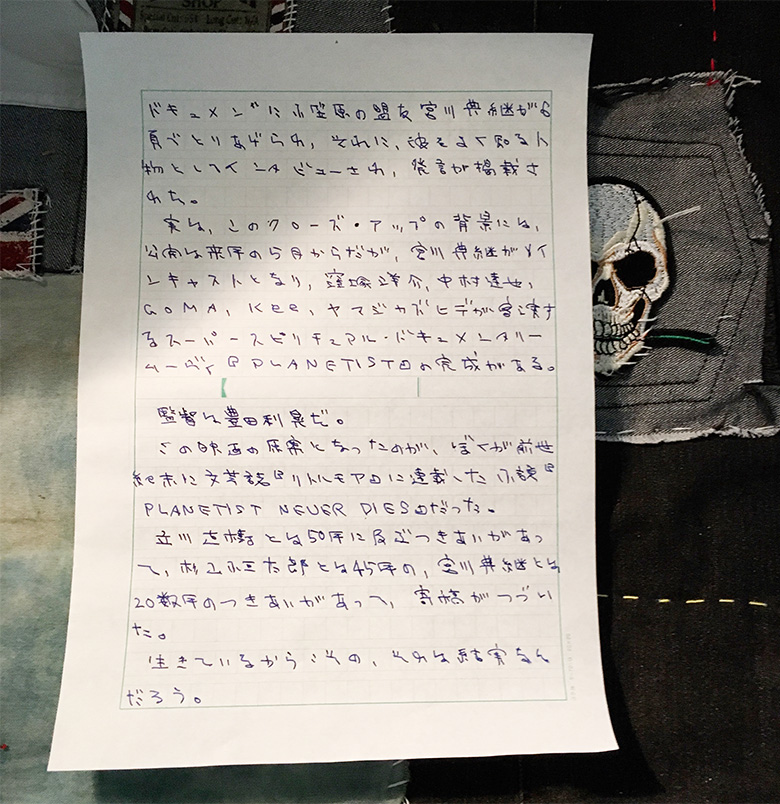
【立川直樹『ザ・ライナーノーツ』まえがき】
音宇宙に記された魂の伝記
どんな音楽も、それを享受する心は個々のものであるべきで、いつの時代にも、優れた音楽は聴く者を未知なる世界への旅へと誘い、愛への憧れを胸にともし、夢見る力を心に授け、不条理に対する怒りを爆発させ、亡き者への追悼の想いを深める。
でないと、音楽は戦意高揚の道具に使われたり、ポイ捨て当たり前の商業活動のネタにされてしまう。そこにはアーティストへの敬意など微塵もない。
衣食住において独自のスタイルを有し、美と結びついたところでの生活思想を確立している者が、音楽、文学、映画、絵画を鑑賞するとき、その精神は輝きを帯びる。直観力のはたらきが、至福の域へと鑑賞者を到達させる。
直観とは、「他人が何と言おうとも、自分がいいと思うことだ」と言ったのは、小林秀雄だが、いや、小林と対談した岡潔だったか、確かに、直観とはそれに尽きる。
小林秀雄がその直観力を駆使して、モーツァルトやゴッホを論じたように、立川直樹は博覧強記の知識を交え、ピンク・フロイドを、デヴッド・ボウイを論じる。アーティストの創作活動時の意識の深奥に潜む葛藤や核心的ビジョンを、鮮やかな手さばきでつかみとってみせる。全身全霊をもってアルバムに耳を傾けることによって、アーティストでさえ気づいてない真理を発見する。
すべては筆跡未踏といってもいいレベルにある。
ライナーノーツは、本来は作品に対する解説にとどまり、内容はレコーディング・データーの羅列か、主観に溺れた論評や批評のようなものだが、立川直樹はここに収録されているJAPANの『TIN DRUM』のレビューにも書いているように「凄い」と言うしかない、さらに「文章で音楽を語ることに対するある種の焦燥感すら抱かされる羽目になったのである」と正直に告白している作品群を、至上の悦びとともに「音宇宙の中を迷い子になってさまよう」(ビートルズ『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』のレビューより)トリップの記録によって語っていく。それは航海記のようだ。
この「音宇宙」という言葉は、本書に何度も使われているが、全50点のアルバム中ブリティッシュ・ロックが4分3を占め、そのほとんどが1970年代に制作されていることが示すように、そこに立川直樹の「音宇宙」があり、そこをさまようことは『スタートレック』さえを想わせる。そう、一枚のアルバムがそうであるだけでなく、取り上げたアルバムの一枚一枚が「音宇宙」に散在する未知なる惑星なのだ。
その「音宇宙」は一様にスィンギング・ロンドンと呼ばれた60年代のブリティッシュ・ロックのオプティティシズムとは一線を画している。
というのも、1970年代の英国は「鉄鋼不況やオイルショックなどが続き、未曾有の不況の時代を迎えていた。失業者は増え続け、都市部でも週に3日の停電が当たり前となり、大英帝国の歴史において、最も貧しく、暗い時代だった」(森達也『ぼくの歌、みんなの歌』より)という時代にブリティッシュ・ロックは民衆の魂を救済する「音宇宙」となって創造力を高めていった。
立川直樹は1970年にはじめてのライナーノーツを書いた。アルバムは本書にも収録されている英国のバンドTHE FLOCK『DINOSAUR SWANPS』である。やがて英国に訪れる暗黒の時代のはじまりに作られたこの作品を立川直樹は「自由」と「未来」という言葉を使って語る。
「彼等は1つのパターンを守らずにいろいろなことをやっている。とても自由な形で演奏している。そして、もっと自由になりたいと願っている。これらが本当に忘れてはならないニュー・ロックの精神なのではないだろうか」と、讃えたレビューは、以下の高らかな宣言でしめくくられている。
「まだロックには限りない未来がひらけているといえよう。ロックは決して保守的であってはならない」
立川直樹が21歳の時に書いたこのレビューは、その後の1970年代以降のブリティッシュ・ロックの、社会に対する強い影響力を孕み芸術性をも追求しながらも驚異的セールスさえ獲得していく歴史を予言すると同時に、立川直樹が若い自分自身の未来にも向けた、魂を鼓舞させるメッセージでもあったのではないか。
1970年にスタートしたライティングは「刺激的なレコードを聞きたいという渇望」(ニック・メイスン『空想感覚』のライナーノーツより)のもとに継続し、およそ半世紀もの歳月が経ち、2018年、70歳を直前に、このアーカイブ・ブックを刊行することになった。
この一冊は立川直樹がその人生において、何を一番信じ、愛していたかを表明する魂の伝記だ。
そして、立川直樹は、この本の最後を飾るレビューを、ブリティッシュ・ロックではなく、ジャニス・ジョプリンの『チープ・スリル』とボブ・ディランの『欲望』を選び、本書のために書き下ろしている。
まるで、初心にかえるがごとく。
決して癒えることのない渇望のおもむくままに。
「音宇宙」へのさらなる果てない旅が、ここからはじまる。
もし私が神であったら、青春を人生の最後に置いたであろうーーアナトール・フランス