プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)
- TEXT:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- Special
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 75-2
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- special 2
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- special 3
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- special 4
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
シーナ&ロケッツ
レッドシューズのリニューアル・パーティーは、ムッシュやケンケンもやってきて、セッションがはじまり、何度も万杯の店内は興奮がヒート・アップしていく。
深夜1時をまわり、ウワサ通りに鮎川誠があらわれる。
客を縫うように飛んでいき、言葉もなく、強く握手する。
目の光が交差する。
全員で、鮎川誠に声援を送り、セッションがはじまった。

それは、ロックンロールが不滅であることを、ロックンロールが多くの死をのりこえてきたことを、鮎川誠の人生がロックンロールに捧げられたものであったことを、いつになく激しく伝えてくる。
熱演する鮎川誠に臨み叫ぶ客の中に店長のリオもいて、ぼろぼろ涙を流している。
そこで、鮎川誠が変わらずロックンロールを歌い、演奏している姿に、崇拝する気持ちさえを抱き、胸を熱くしている。

ぼくらは鮎川誠と、シーナを崇拝している。
シーナも不滅である。
シーナはいまも、鮎川誠と生きている。
ロックンロールが、この世にある限り、そこには鮎川誠とシーナがいる。
鮎川誠を見ていて、ある瞬間、天啓のような想いが訪れた。
それは、チャック・ベリーが、そうであったように、鮎川誠という存在様式こそがロックンロールであることを、認識していた。
鮎川誠には一度、インタビューしたことがあった。それはレッドシューズの二代目オーナーの門野との共著『レッドシューズの逆襲』のためのものだった。
インタビューの場は開店前のレッド。シーナも同席し、早乙女が彼等をドローイングした。
このインタビューのなかに、シーナは鮎川誠に寄り添い生きている。
以下、転載。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
あの頃、60年代とはちがった意味で、アーティストたちは状況を変えようとしていた。60年代には、アメリカやイギリスの新しいロックの衝撃をうけるばかりで、憧れに突き動かされて、暗闇の中を突っ走ってるキッズにすぎなかった。
70年代には再びバンクの衝撃がやってきたが、それを全身でうけとめたのは主に、まだライブハウスで奮闘している売れないバンドだった。
70年代末に、やっと中心へ至る軌道の扉が開かれはじめた。
時代が変わる予感が、東京でたちのぽってきた。
自分たちのやりたいようにやればいいんだと、あちこちで弾けていった。それは、マシンガンを思わせた。
シーナ&ロケッツは、その頃、九州から東京にやってきて、強烈なビートの鏑矢を状況のど真ん中に射ち放った。
時、同じく、〈レッドシューズ〉も狼煙をあげた。
それは、東京革命と呼んでもいい、正に新しい時代の幕開けだった。
森永 : 新宿の〈ツバキハウス〉で『レモン・ティー』を聴いたとき、衝撃があった。何か新しい時代がはじまるみたいな。
シーナ : 〈ツバキ〉でね。
鮎川 : オレたちは78年に東京に来て、79年、アルファから細野(晴臣)サンのプロデュースでデビューしたんよ。その頃、細野サンとよく行ってたのが、原宿のなんだっけ?
シーナ : 〈カルデサック〉。
鮎川 : その〈カルデサック〉のオーナーが、シーナと同じ北九州の若松出身で、高校もいっしょ、若高っていう。それで、エーッてビックリして。
森永 : じゃあ、〈レッドシューズ〉も細野サンといっしょだった?
シーナ : 細野さんがあたしたちのレコード、プロデュースするっていうんで、打ち合わせやろうってね。カフェ・バーっていうのがあるっていうから、カフェ・バーって何? コーヒーあるからカフェっていうのかねって話したりして。
鮎川 : オレたちも細野サンも酒飲まんからね。打ち合わせで〈レッドシューズ〉行って、コーヒー飲んでた。
シーナ : 打ち合わせっていっても、仕事の話、何もしないの。お互い好きなことだけ話しして。何を作ろうなんて話ないの。
鮎川 : そのうち、〈インクスティック〉がオープンして、それで輪郭がハッキリしたよね。それまでの酒場とぜんぜん違いよったよね。オーナーの松山サンちゅうハッキリ主役がおってさ。スーツ着て、あの背の高いカッコイイ松山サンが店にいると、安心できる感じはあったよね。
森永 : 〈インクスティック〉によく出てたよね?
鮎川 : ライブはよくやったなぁ。
シーナ : 芝浦のほうね。あそこで動員の記録作った。1500人とか入って。東京で一番カッコいいライブ・ハウスだったよね。
鮎川 : 新宿〈ロフト〉とか〈屋根裏〉とか、ああいう熱も残しながらオシャレやったよね。
シーナ : ニューヨーク感覚よね、運河沿いのソーホーみたいな、特別な感じ。
森永 : 東京が一番面白くなっていった頃ですね。79年から83年まで。
鮎川 : オレたちはなんちゅうか、アルファ・レコードとYMOがあってね、細野サンとか高橋幸宏とか、東京でずーっといつもシャレたところにいた彼らを通じて、東京体験してた感じよね、最初は。やっぱし、音楽の趣味がすごくマニアックで、遊びもマニアックな東京の粋なヤング・ロッカー? ロッカーっていっても、汗臭くなくて、ディープな音楽にこだわるけど、表向きはあんまりロックじゃなくてっちゅう。細野さんたちは、ミステリアスやったね。アルファ・レコードもね、オレたちが入ったとき、そんなに他のレコード会社のことは知らんけど、随分とかわっておった。
シーナ : 文化があって、ガーッと進んでてね。
鮎川 : それで、代表やってた川添(象郎)サンと村井(邦彦)サンが、細野サンたちよりいっこ先輩たちで、いい感じでさ。その前にオレたちがいたレコード会社は、デスクにスポーツ新聞がひろがってるような旧態もいいとこ。そこからアルファに移ったから。すごいオシャレでさ。行ったその日にふたりで笑う出来事があったんやけど。ひとり社員が来てさ、そこにもうひとり社員が来たら、「キミ、そのネクタイ、おかしいよ」って(笑)。みんなアカ抜けてて、センスよかったんよ。
森永 : 嫌味じゃないでしょ?
鮎川 : ないない。プライドがあって、自分たちは業界に新しい風送り込んでるっちゅう。いま思えば、すべて新しいことやった。レコード会社なのに、そういうファッションていうか、トレンドやね、いまみんな簡単にトレンドっていうけど、インターナショナルな動きと社員が連動してた。そのアルファ・レコードが、コンサートあって打ち上げってゆうたら、その場所、面白いところ用意してて。
シーナ : そうよ。〈1999〉借り切ってパーティーやって、中にプールがあったから、社員がそこ飛び込んでんのよ。
鮎川 : その頃、アルファのパーティーゆうたら、メディアのリーダーたちが一堂に会して、そんなの他になかったんよ。デザイナーとかイラストレーターとか、カメラマンとか。それで、細野サンのすごかったところは、糸井重里サンとか、新しいクリエーターをすぐに巻き込むんよ。スネークマンショーも、そうやけど。
シーナ : 仲畑貴志サンとかもね。
門野 : 糸井サンはシーナ&ロケッツの詞も書いているんですね。
鮎川 : 詞も書いてる。細野サンが糸井サンいいかも知らんとかいって。フォトグラファーもスタイリストもヘアメイクも細野サンが決めるんよ。驚いた。
森永 : スタイリストは誰がついたの?
鮎川 : YMOとつきあいだした頃、(高橋)幸宏が〈ブリックス〉っていうブティックやってたんよ。それで森英恵ビルでファッション・ショーやったときやね。そのとき幸宏の縁故関係で加藤和彦サンとか、のちに大事な作詞家として組むことになったクリス・モスデルとか、いろんなアーティストたちがモデルやるっていう面白いファッション・ショーで、オレもモデルやった。それで、ファースト・アルバムでは、幸宏と奥さんがスタイリスト。その次誰やったかなアレは? 三宅一生のものすごい服用意してて。ところがオレたちは基本的にブリティッシュ・ビートやろ。バンク、ニューウェイブの匂いが飛んでしまうような服で、絶対に着られんって、スタジオで大立ち回りになって、もう帰るみたいなとこまで険悪になって。結局、自前の服でいいって落ち着いて。あのときロス行って帰ってきたばっかりやったけん、ツートン・ブームでね向こうが。オレたちがフツーに好きな感覚で、それ着たんよ。
門野 : そのジャケットすごくカッコいいんですよ。
鮎川 : まあ、あれでよかったよね。フツーのスーツで。
森永 : その頃から、ロックにたくさんのクリエーターがかかわりだしたよね。

鮎川 : そうね。いろんなアーティストがロックに複合的にかかわりだした頃ね。そんななかで、〈レッドシューズ〉ができたって感じよね。
森永 : 一方にアルファの川添サン、村井サン、それに細野サンがいて、一方に〈レッドシューズ〉の松山サンがいるっていう時代ですね。でも、両者はぜんぜんタイプが違ったでしょ?
鮎川 : 不良だったね、松山サンは。なんかね、ハッキリしてたんよ。
森永 : 松山サンはスパイダースの後援会やってたんですよ。
鮎川 : のちに人から聞いて、あー、そうかって感じやったもん。
シーナ : やっぱりロックなんだよ。
森永 : じゃあ、ミュージシャンではないけど同じような匂い感じてた?
鮎川 : うん。ものすごいロック感じよった。〈レッドシューズ〉はブライアン・フェリーの大きな写真があったんが、ひとつの象徴だったよね。なんかこじつけかも知らんけども、昔、博多でやってる頃、ダンスホールっちゅうのがあって、いろんな客が来るんよ。で、中には酔っ払って調子にのった客もいて、そんとき、強烈なロックやブルースやると、つけこまれんのよ。そこで、変に、流行りの『ダイアナ』とかやると、オレの得意の歌だってのさばってくる。だから、ジェスロ・タルの曲やると、ぶつぶつ言いながら帰って行く。〈レッドシューズ〉には、そういう力があったかもね。えらい筋金入りのロックの雰囲気が底辺にあって。表はね、そんな感じじゃなくて、割とオシャレなんやけど。流れてる音楽も、そうやったけど。
シーナ : ストーンズとかヤードバーズとかね。
(中略)
森永 : で、門ちゃんとの付き合いは?
門野 : ぼくがおふたりに会ったのは、90年。
鮎川 : そうなん、90年?
門野 : ぼくは若い頃からシーナ&ロケッツの大ファンで、おふたりが店に入ってきたとき、ウワーッて思って。話しかける機会ないかなと考えていたら、手に、この本(『ビッグビートvol.1』)を持たれていたんで、見せてくださいって言ったんですよ。すごいカッコいい本なんで。(とふたりに見せる)
鮎川 : (手にとり)オレもこれ何回か読みかえしたし、自分のインターネットのページにも全文のせたしね。そうねん、これ、90年ね。
シーナ : ストーンズが初来日した年ね。
門野 : で、見せてもらって、コレ欲しいって思ったんですね。それで、シーナさんに、コレ何処で手に入るんですかって聞いたら、シーナさんが誠さんに、「マコ、この子にコレあげて」って言ってもらって、いただいたんですね。いまでも、ぼくの宝物です。
鮎川 : オレ、もっと昔から知っとる気してた。90年っていうたら、自分たちのバンドの歴史でいうと、オリジナル・メンバーの浅田(孟)、川嶋(一秀)がやめて、オレたちふたりだけになってね。で、ストーンズ観に行ったとき、誰かここに来てる奴のなかからドラムとベース見つけるべきだなって思ってた。これ観に来てない奴とは絶対オレはやれんと思ってた年やね。とんでもない大事件やったからね。
門野 : ストーンズ初来日のときは、バーナード(・ファーラー)が招待してくれて行ったんですね。で、ラウンジの外でおふたりをお見かけしたんですよ。そしたら警備員ともめてる。ここから先はダメといわれて、でも、オレたちはロン・ウッドに会いに来たんだ、お前ら、ジャマするなって押し問答をくりひろげてて、いやーカッコいいなって、うしろでドキドキしてました。
鮎川 : 警備員ともめながら、毎日行ってた。〈レッドシューズ〉にはロン・ウッドが来よったんやろ。どっちが先だっけ。ロン・ウッドが来るよっていって、オレたちを誘ってくれたんやっけ?
門野 : ロン・ウッドが来るという情報が入って、すぐ電話したんです。
鮎川 : そんで、あのトカゲの入った酒、いたく気に入って、ロンが飲んで、あんときは奥サンも来てたやろ。あんとき忘れられん思い出は、ロンが手が痛いんよっていってたから、シーナがじゃああたしが治してあげるゆうて。
シーナ : ヒーリングでね。
鮎川 : 治してあげたんよ。それで、家に帰ったら、留守電に、ロンから手が動くようになったってお礼のメッセージが入っていて。すごいマメな人やゆうか、優しい人やね。でも、オレたちにしては、すごいことや。一生忘れられん思い出やね。ジョーイ・ラモーンも留守電にメッセージ残してて、それはすごくちっちゃいマイクロ・テープなんやけど。
森永 : それ、とってあります?
鮎川 : あるよ。サイコーの宝物。でもね、ロンが〈レッドシューズ〉に来るちゅうのが、オレが知ってる〈レッドシューズ〉だけに、すごいことやと思った。そんな店、他になかったやろ、東京で。気取った店は別として。接待でいく店も別として。ミュージシャンが好きで行くちゅう店は他にない。やっぱり、ロックが流れてて、お客さんもロックが好きな人ばっかし来る店やないと。それじゃないとね、訳わからんミーハーばかりの店だったらね。
森永 : 居心地よかったんだろうね。
シーナ : やっぱり東京文化みたいな、独自のね。外国にも何処にもないっていう。そういう何かが〈レッドシューズ〉にはあったよね。
鮎川 : 〈レッドシューズ〉ができた頃って、パンクからニューウェイブへ流れが変わって、東京によく外国からアーティストが来てた。クラッッシュ、ラモーンズとか、ストレイト・キャッツ、トーキング・ヘッズとか。オレの友だちのカメラマンに、ボブ・グルーエンっておって、その頃、ニューヨークから東京に移り住みよってね。ニューヨークにいるより東京にいた方が、アーティストの写真がたくさん撮れるゆうて。そのくらい来てた。東京が呼ぶ力持ってて、なおかつYMOみたいな東京ポップってゆう名前で、逆に海外に発信しよったりで。
シーナ : みんなその頃、東京が好きなんよ。だからわたしたち外国行ったら、フロム・ジャパンなんていったことない。いつもフロム・トーキョーっていってた。
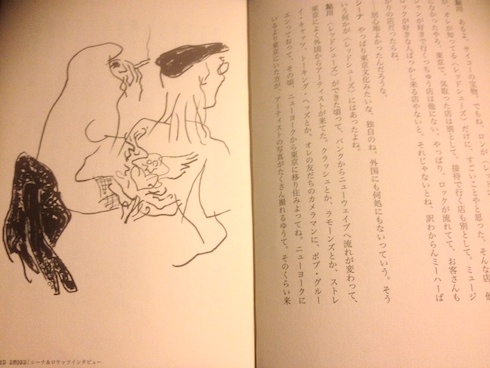

森永 : そういう動きの中心に〈レッドシューズ〉もあったわけで、酒は飲まなかった?
シーナ : 90年頃は、飲んでたよ。わたし、抱えて帰ったことあるよ。
鮎川 : シーナ&ロケッツから浅田と川嶋が脱けて、ジョニー(吉長)がヘルプでメンバーになったんよ。それで、他にユミちゃん、モモちゃんとか。
シーナ : ダンサーが入って。
鮎川 : アルジアみたいなジャマイカ人が入って、それで打ち上げは〈レッドシューズ〉。オレたちの〈レッドシューズ〉の日々がちょっとつづいたね。何か、祝いごととかは、すべて〈レッドシューズ〉。オレ、グデングデンに酔ってひっくりかえったことあるよ。テキーラ、よく飲んで。テキーラ飲むと、ホットになる。ジョニーがまたいうんよ。コレ、メキシコの労働者がつかれたとき飲んで元気つけるって。ホント、飲むと、ピシャーンってなってさ。でも、最後、ドーンって酔うけど。
森永 : でも、明るい酒でしょ?
シーナ : うん。明るい、明るい。酔うと踊るもん。
〈レッドシューズ〉でのインタビューは1時間程のセッティングだったが、話すうちに、酒が入っていたわけでもないのに、想い出が想い出を呼んだのか、会話に熱がこもってきた。
〈レッドシューズ〉に出入りしていた頃の想い出は、きっとふたりにとって、ロックの冒険に、何も恐れることなく、全身懸けて挑んでいた頃のスピリットを呼び起こすのだろう。
話しは勢いづいて、僕らが60年代、70年代、どんな音楽に夢中になっていたか、東京のどんな店でロックを聴いていたか、時空を駆け巡り、けっきょく、3時間喋りつづけた。
多分、80年代の〈レッドシューズ〉では、こんな夜はいくらでもあったのだろう。
本当に、好きなロックの話になると、鮎川誠もシーナも、キッズのように眼を輝かせ、声を弾ませ、生き生きとなる。
ピュアだよなーと思った。
その夜、帰宅し、『ロックンロール・ハート』に収録されている好きなヴァージョンの『レモン・ティー』を聴いてみた。
このビート!! この歌!!
80年代はじめの東京を最初にビートで踊らせたナンバー!! あの頃の〈レッドシューズ〉のいかれたざわめきも蘇ってくる。
『レモン・ティー』は永遠の名曲だ。
というインタビューだった。
ふたりと語り合ったあの夜を思い出す。
きっと、何度も、何度も、思い出す。
シーナ、ありがとう。
いつまでも、いつまでも、俺たちは、貴方を愛してるよ。
