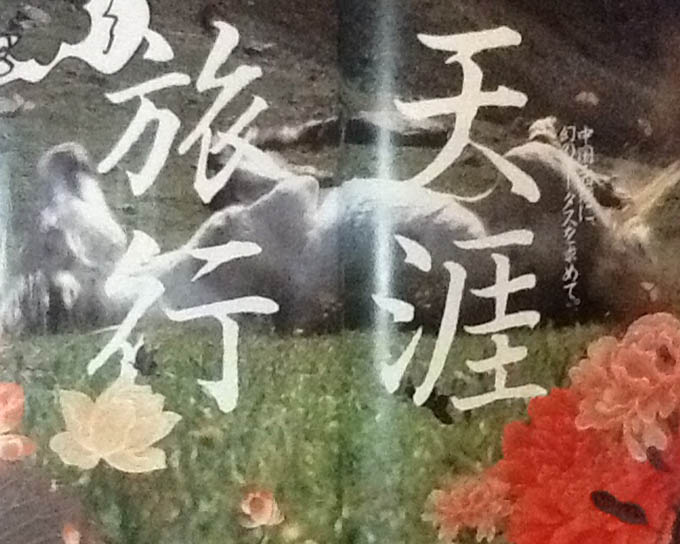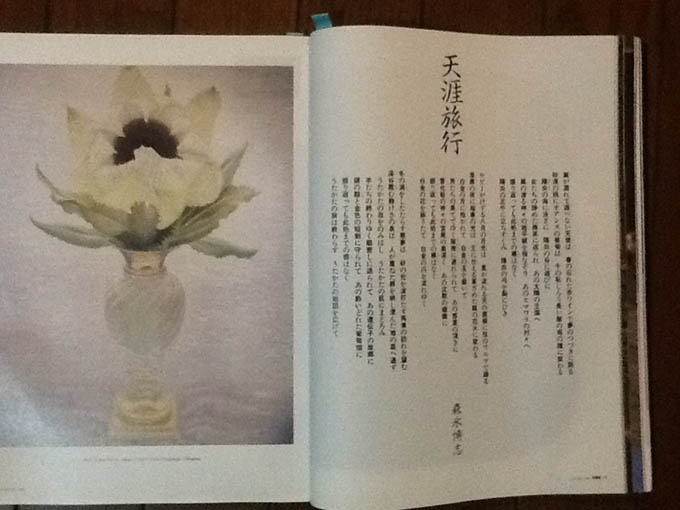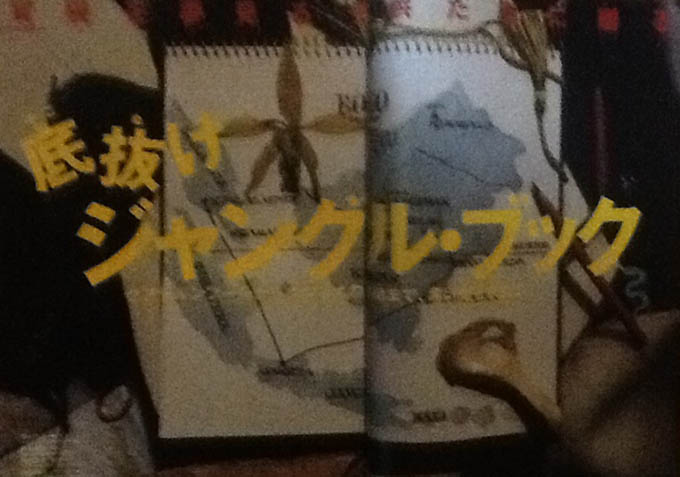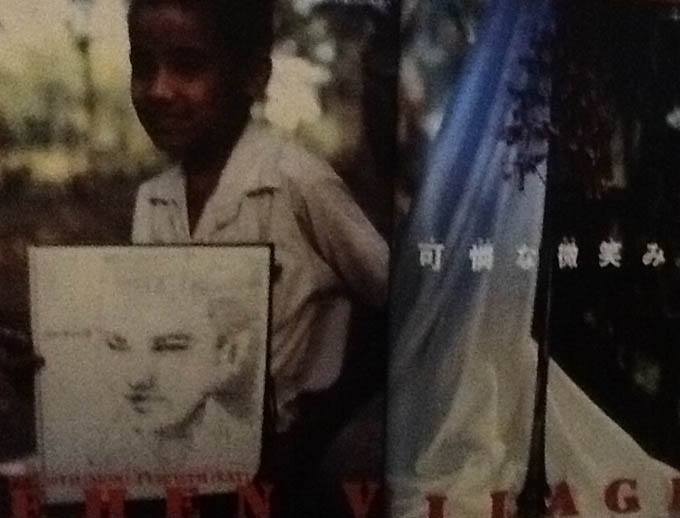プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)
- TEXT:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- Special
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 75-2
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- special 2
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- special 3
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- special 4
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
スノーロータスを発見したことにより、ぼくは完全に植物に憑かれていった。
その兆候は、ボコダに行く2年ほど前にあった。
キッカケは何であったか? 忘れてしまったが、エディター仲間だったキョーイチこと都筑響一といっしょに珍奇植物を収集していた。藤沢にアフリカ産の珍奇植物を扱う店があるのを知り、キョーイチの運転する車で、トニー谷を聞きながら買いにいった。
アフリカ産珍奇植物は鉱石のような物体だった。
植物が想像を絶する姿をしているのを初めて見たのは、マウイ島。ハレアカラの山頂に進化植物の一種、シルバースウォードがレインジャー部隊に保護されて生存していた。それは銀の刀のような形態をしていた。
マウイには、そのような進化植物が300種ほどあったが、白人資本家がトロピカルプランツを持ち込んでプランテーションを作ったことにより生態系は破壊され植物的な意味での「悪貨は良貨を駆逐する」結果となり、ほぼ絶滅してしまったとされる。
それでもシルバースウォードを見て、植物に未知なる神秘を感じ、好奇心に駆られた。
次に八丈島の植物園で食虫植物を見て、さらに好奇心は増した。
その後、ロンドンの自然史博物館のショップで空中植物を見た。宙に浮かぶティランジアは衝撃だった。買うことはできるが、日本には持って帰れない。帰国し、すぐに親しくしていた植物商に電話をしティランジアのことを聞いた。
その時点では日本にティランジアは入ってなかった。手に入れたいとオーダーすると、ロスの業者から輸入してくれた。
原宿のギャラリーでティランジア展を開催した。原産地が中南米だったので、ギャラリーにインカ帝国の遺跡のインスタレーションを工作し、そこにティランジアを配置した。
その後、カリブの島々を旅したとき、電線に密集しているのを目撃した。ティランジアはカリブがふるさとだった。ハリケーンが来ると、ティランジアは風で北米大陸にはこばれてゆく。
そのころ、横山氏と再会し、花の話しで盛り上がった。
そして、ぼくらはスノーロータスを探す旅に出た。花を見つけ、横山氏は花の肖像画を100号のキャンバスに描き、ぼくは詩を書いた。
その翌年、今度は横山氏の方からプラントハンティングの提案があった。
それは旧名ボルネオ、現カリマンタンのセントラルジャングルに生きるブラックオーキッドを探しに行く旅だった。
メンバーは4人。秘境ツアー専門のコーディネーター田中氏と写真家の園木氏を誘った。行程はまずは名古屋からクアラルンプールに入り、郊外に暮らす副島さんを訪ねる。会うのははじめてだった。副島さんの息子が遊び友だちだった。彼は東京にいるが、副島さんに訪ねて行くことを伝えてもらった。
訪ね、蘭に魂を奪われた数奇な運命の話を聞いた。
1970年代中頃まで副島さんはJALの生え抜きの幹部だった。しかしJALはすでに官僚の天下り先と官僚のご令嬢たちを優先的に国際線のスチュワーデスに採用する腐敗構造に骨の髄までおかされていた。
しかもトップの座をめぐる企業内での争いも醜く、副島さんは企業人であることにうんざりしていた。
ロンドン支店長、バンコク支店長と海外生活がつづいたが、バンコクでは本社からの任務でジャングルに蘭の調査と採集にはいった。初めて見た野生の蘭に、副島さんは魅せられていく。熱帯雨林が育む美に神の息づかいを感じ、任務をわすれていった。
副島さんの心の中で、異変が起こった。
「私は野生の蘭を採集して日本に送る任務についていた。でも、ジャングルで野生の蘭を見て、気が変わった。適当にごまかして、日本に送るのをやめよう。企業人もやめよう。残りの人生を、熱帯アジアの何処かで、蘭とともに生きよう。私は、そう決めていた」
クアラルンプール支店長になったとき、赤軍派のハイジャック機がやってきた。副島さんが空港内での陣頭指揮をとり、「私は、国家を命がけで変えようとしていた彼らにシンパシーを感じていたので、資金を渡し、中東へ送り出しました」。
直後、副島さんはJALを辞めた。そのままJALにとどまっていたら社長への道が約束されていたが、その将来を、副島さんは蘭のために捨てた。日本にいる家族とは財産を与え離縁した。クアラルンプールの郊外、森の中に新居をかまえ蘭のガーデン、温室もこしらえた。
副島さんの新しい人生がはじまった。すべての時間を蘭にそそぎこんだ。タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシアのジャングルを探検し、蘭の原種を収集しガーデンで交配し品種の改良に情熱を傾ける。
クアラルンプールは気候が素晴らしかった。日中は湿気と暑気で人にはきついが、蘭には最適な環境だ。毎日夕方にはスコールが降る。ひと雨降れば、気温はいっぺんに下がり、夜はクーラーもいらない。熱帯夜が一夜もない。
副島さんは先見の明があったのか。蘭の人気は世界的に高まっていった。副島さんも新種の改良に成功し、世界の品評会で注目され、品種によっては何百万の値がついた。しかし、副島さんは蘭との共生こそが生き甲斐であって、金儲けに興味はない。
花を求める心の芯にあるのは美への憧憬だ。それがどれだけ人の生き方に強い作用を及ぼすか、副島大老を訪ねて教えられた。
副島さんはクアラルンプールで、その蘭に魅せられた人生を終えた。
葬儀には数人の若い現地人の妻が出席していたよ、と苦笑いする息子から聞いた。クアラルンプールはイスラム国家なので、一夫多妻制なのだ。
ぼくらの旅はマレーシアからインドネシアに向かった。ジャワ島のジャカルタ経由でボルネオ島のバリクパパンについた。そこから車で、山を越え、サマリンダという町へ。サマリンダからセントラルジャングルまではマカハム河をモーターボートで行く。2日かかる。
この遡行がかなり危険だった。というのも、日本や中国の業者が建材用にジャングルの樹をガンガン伐採し、河には上流から大量の丸太が流れてくる。丸太に船が衝突したら転覆し、溺れ死ぬこともある。河は水深も幅もある大河だ。だから、荷物はロープで縛りつけ、ぼくらも荷物にシッカリしがみついていた。
マカハム河は赤道直下を流れている。日中はあまりに陽射しが強く生活環境は厳しい。一日目の航行を終え上陸した地はムラムンタイ、イスラム教徒の村だった。ホテルもコテージもない。宿とは名ばかりのボロ小屋に泊まった。部屋にはちいさなベッドがひとつ、蚊帳にかこわれていた。他に何もない。
今回の旅も怖れるものは多々あった。
一番は病気。マラリア蚊に刺されたら死に至る、かもしれない。他にコレラ、破傷風、B型肝炎。何種類もの予防注射をうったし、飲み薬も用意した。毒を持った蛇、サソリ、蟻、ヒル、心配の種は尽きない。
ジャングルは快適とは無縁の環境だ。そんな奥地に幻の花は咲いている。
村の建物は川面よりかなり高いところに施設されたデッキの上にあった。月下の村は、日中の熱気も去り、川風も快適で村人は夜通しお祭り騒ぎをしていて、郷愁に包まれた。翌日は村の周辺をめぐると、この水域にしか棲まないという淡水系のイルカがいた。
そこはのちに映画で見たアバダーのような村だった。
二日目にセントラルジャングルの入り口の村、メラクについた。そこでジャングルトレッキングのナビゲーターと会った。名はジョー・ペリー・ジュアン。ボルネオのセントラルジャングルの村で生まれたダヤク族、29歳。ダヤク族のルーツはモンゴルだ。
ジョーはジャカルタの大学でジャングルの植物学、動物学、民族の歴史などを学び、学生ボクシングのチャンピョンにもなっている。ジョーの体は筋肉の塊だ。ジョーはボルネオのジャングルに関する専門書を三冊も書いている。イギリスの探検隊を何度も奥地に案内している。さらに、ジョーはチベットにも行き、チベット式のマッサージ術も修得し、医者でもあった。
船着場の村メラクからジープで赤土の土煙に包まれて突っ走り、プラントハンティングのベースキャンプになるエヘン村に到着した。村は10軒ほどの小屋とロングハウスという高床式の細長い長屋があるだけで、電気も水道も宿も食堂も商店もない。
実はつい最近まで、エヘン村は首狩りをしていたという。
ぼくらは酋長の家の離れに泊めてもらった。食事は自炊になるので、ひとりスラバヤ島生まれの若者を炊事番としてムラムンタイで雇った。食事は米を炊き、ジャングルで採取した植物の炒め物。酋長は毎日たくさんのフルーツを届けてくれた。
風呂もシャワーもなく谷間の泉で水浴びをする、原始の生活だった。
それでも何の不便を感じることもなく、ぼくらは村人たちと親しくなり毎日をエンジョイした。
ジャングルは驚異だった。毎日エヘン村の案内人とジャングルに入り黒い蘭を探した。そこは道など開かれてなく、雨が降ったら水浸しになる。それも熱帯の暑気と湿気が混じり合い、ジャングルの中の空気は呼吸が苦しくなるほど不快だ。
ボルネオのジャングルは、アマゾンと植生を異にし、陽を通さぬほど密生している。案内人は刀で木の枝や蔓を切り払いながら前進してゆく。川には丸太が一本渡されてるだけだった。
ジャングルのエキスパート、ジョーが植物の効用を教えてくれる。すべての植物に薬草的効用がある。いまだ特効薬も開発されてないマラリアにはクルミのようなナッツ。捻挫、打撲には患部に当てておけば一晩で治る草。凄いのは摂取すれば体の細胞が活性化し、大人の手や顔の皺が消え、白髪も黒くなり、腰や背中の神経的な痛みも消えるとジョーがいう薬草もあった。
ジョーは言う。
「ジャングルで生きている人たちは長生きする。自分の祖母は108歳まで生きた。普通、100歳までは軽く生きる。というのも、私たちはジャングルこそ命の源と思っていて、その源の自然しか食べないからです。だから私たちは病気知らず、男だけでなく、女も力仕事します」
ジャングルに入る度に、元気になっていく。滝のような汗をかき、毒気がぬけていく。日暮れにはエヘン村に戻り、谷間の泉で村人たちと水浴する。お清めだ。食べる物はジャングルで採取した物だけ。毎日生きかえっていく。
4日目のトレックで焼け野原にでた。ジャングルにも農耕民はいて、彼らの農法は焼き畑だ。それで土を肥やす。火をつけたのはいいが、強風に見舞われ、火に勢いがつき広域を焼き尽くすことが多々ある。プラントハンティングの数年後、ボルネオのジャングルで大規模の火事がおこり、1ヶ月ほどつづき、シンガポールまで大量の煙が流れた。
焼け野原も火事の跡だった。その一画に砂浜があった。
このプラントハンティングの記録も「翼の王国」に発表した。それは、こんな終わり方をしている。
♪☆☆☆ ★
満月の夜にぼくたちはクアラルンプールのアポロ・ホテルにもどってました。このホテルはヨーロピアンに人気のある安宿で、四人で泊まれるファミリー・ルームが一部屋50ドルでした。ぼくらはあんまりお金を持ってなかったのです。ギター以外なにも買いませんでした。
でも、横山さんのスケッチブックをひらくと、そこに自慢のお土産がたくさんあります。
ぼくらはちゃんと黒い蘭を見つけたのです。蘭の好きな大人ならみんなが一目見たいとあこがれ、日本でこの蘭をもっているの人は資生堂の社長だけという、幻の蘭を見つけたのです。
黒い蘭はいまのインドネシアの大統領夫人が、この花は自分の国の大切な宝物だから、絶対に海外にもちだしてはいけません、と乱獲を厳しく取り締まり、手あつく保護していました。それも、ジャングルの中で。
むかしはヨーロピアンが船に乗って、この赤道の島のジャングルに蘭を採りにきました。蘭や蝶はヨーロピアンのあこがれをさそいました。宝石よりも価値があったのです。それは見たこともない野生の美しさと、他所ではよほど丁重にあつかわなければ死んでしまう貴重な命のせいでしょう。
蘭と蝶は、森の精霊です。よくいわれる「夢のようだ」という感動の正体です。
ぼくたちは蘭のなかでいちばん奥地に咲くという黒い蘭を、ついに発見しました。
蘭は、副島さんから聞いたように、高い木の上の方にはいませんでした。ジャングルをいくら探しても見つからず、たどりついた焼け野原の先の、海の砂浜のような、そこに低くしげるブッシュの中に、森の番人に守られ隠れていました。
ブラックオーキッドは、花の全体が黒ではなく、ヒトデのように広げたエメラルド色の花ビラの中心に墨汁をぶつけたような漆黒の紋様をタトゥーのようにしるしてました。
ブラックオーキッドは、10年前に火事で全焼してしまった森のあとの、栄養分たっぶり、美味しさ抜群の土の茂みに、まわりを食虫植物たちに守らせて隠れすみ、ジャングルのエキスをたっぷり吸っていたのです!
秘境と呼ばれる地に、幻の花は咲いている。
東京にも、秘境はある。遠くは、海原を1000キロ越えた絶海の孤島群、小笠原諸島、その先の三つの硫黄島を含む火山列島。小笠原諸島へは何度も渡ったが、そのとき心は花より巨大な水晶や鯨、銀河、島人に魅せられていた。
最も近い秘境は伊豆七島のひとつの青ヶ島だ。
今でこそヘリコプターが就航しているが、その前は、船便のみ。航路は難路だった。そこには、黒潮が流れ込んでいるため、潮の流れが強く、天候がちょっとでも荒れると、船便は欠航した。話しに聞いたところによると、船便の欠航が続き、一ヶ月間、青ヶ島に閉じ込められた旅人もいた。世界でも稀に見る秘境だ。
伊豆七島の大島、三宅、御蔵、八丈、新島には、よく行っていたが、青ヶ島は何度渡ろうとしても、船便の欠航で断念していた。それで、余計、秘境に寄せる想いは強くなっていった。
大島に通ううちに、流され者として、大島にやって来た源為朝のことを知った。
為朝は、京都での保元の乱に敗れて、大島に流されてきたとき、20歳になったばかりのまだ若者だった。
為朝は早熟の暴れん坊で、京都での乱暴狼藉が過ぎ、13歳で親に勘当され九州に追放された。しかし、為朝は改心せず、九州でも暴れまくり、絶対服従の掟であった朝廷の召喚にも逆らった。そのため父の為義は解官の憂き目にあった。武家の名門と謳われた家柄を汚す天下の親不孝者である。
京都で勃発した天皇家の争いに勇んで参じた為朝は、敗軍の側の武将として罰せられ、1159年に大島に流された。当時は京都が都だったので、伊豆大島は人も住まぬような隔世の島だった。ちなみにその33年のちに源頼朝の鎌倉幕府が誕生する。
という史実を知ったとき、ぼくはそのときの為朝にトランスしてみたくなった。
というのも、日本史における為朝は戦の功績が何ひとつなく大島で、その悲運の運命を閉じた武将と見なされているが、実際はどうだったのだろう?
若い為朝がその目で見た世界は、大島の大自然である。およそ860年前の活火山島だ。島の中心には三原山が噴煙をあげてそびえ、望む本州には霊峰・富士、黒潮の流れ込む海洋にはイルカや鯨が群れて遊んでいただろ。
海は今より遥かに美しく、陽光はその海原を鮮やかに彩り、野生に生きる動植物は島のいたるところに自然の王国を築いていただろう。
子供のころから、魑魅魍魎が跋扈する京都で争いに明け暮れ、諸行無常の響きに接していた青年の五感は大島の大自然に触れて精気に満ち、心は目覚めていったのではなかったか。
この世には人智を超えた世界があり、神性は都の神社仏閣ではなく、大自然にこそ宿っていることを。聖人も、然り。
そう想えるのも、為朝は島流しの境遇でありながら、伊豆七島の他の島々に舟を出し、さらに黒潮圏を遥か彼方まで遠征した伝説を残しているからだ。
都会ぐらしの人間が古今東西問わず、それこそ、パリからアフリカに渡ったランボー、同じくサン・テクジュペリ、タヒチへ渡ったゴーギャン、アメリカのビートニク、ヒッピーなど、自然回帰する営為はいくらでもあった。
為朝は、そんなナチュラリストの先駆者ではなかったか。
為朝の秘境をめぐる旅は青ヶ島にも至る。
その旅は「南総里見八犬伝」の作者・馬琴が為朝を主人公にしたヒロイックファンタジー「椿説弓張月」に書いている。
「全島民が親族のように仲良く暮らし、たとえば、とれた魚なども家ごとに同等に分配し、漁が少ないときでも切り分けて、分配にもれる家がないようにつとめている。その有様は実に剛直寡欲、そして素朴さのなかに誠実味にあふれていた」
そう、為朝は青ヶ島を語る。
2001年の夏の終わり、やっと青ヶ島にヘリコプターで渡った。目的はタメトモユリを見ることだった。タメトモユリは伊豆七島の他の島々にも分布しているが、青ヶ島のユリが最も純正をたもっている。だから、青ヶ島に渡った。
しかしシーズンならば、200人ほどの島民が暮らす集落内でも見ることはできるらしいが、すでにシーズンは終わろうとしていた。
島内を探すうちに、カルデラの原野にひっそりと咲くタメトモユリを発見した。空は真っ青に澄み渡り、太陽の光が降り注いでいた。光を浴び純白に輝く花弁は若々しく野生の精気をみなぎらせ、ぼくはこれほど力強い姿をした花を見るのははじめてだった。
それは美しさを超え神々しくさえあり、ぼくはそこに激しくタメトモの魂を感じていた。
この花とともに絶海の孤島で島人は何百年と暮らしてきた。
島人が剛直寡欲ならば、花も同じである。
現代にあって、人が生きるには余りに環境が厳しすぎると、東京都庁が全島民の移住を好条件で提案したが、全島民が青ヶ島に暮らす道を選んだ。
いまも隔世の島に咲くタメトモユリは、われわれの想像も及ばないほど強く島人の心とむすびついている気がした。