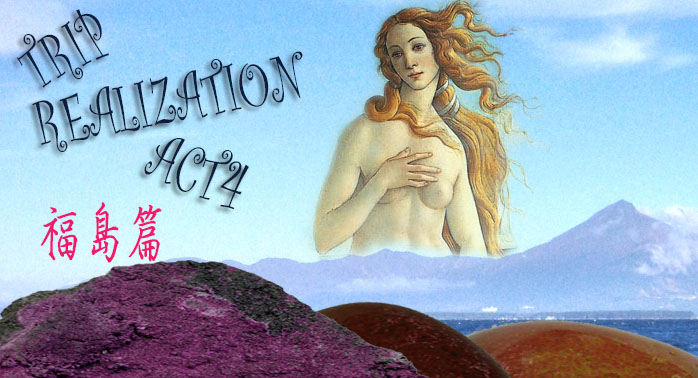
1
標高は1000mもないのに猪苗代湖からうけた第一印象は1989年に旅したアンデス、標高3800mの高地にひろがるチチカカ湖だった。
はじめて猪苗代湖に行ったのは真夏日のことだった。
しかし、今日はすっかり秋の日、見事な青空のした猪苗代湖には白波が岸にむかって走っている。
その光景はもう湖ではなく海だ。
湖面は目にしみいるほど青々としている。
新鮮な印象に胸を高鳴らせている。






猪苗代湖にまつわる奇怪な風聞を最初におしえくれた方は地元の後藤さんだ。
「311の前日にすごいことがあったんだ。猪苗代湖の湖底から大きな重い石がうかびあがってきた。地元の人が、それを発見し、何かの不吉な前兆かとこわがっていたら、翌日、311だった!」
という話を後藤さんから聞き、
「その石は、隕石ですかね?」
「たぶん。巨大隕石が、ここに落ちてきて湖ができたんだとおもう。外輪山、ないからね」
「じゃ、火山湖じゃない?」
「そういうこと。湖底に湧き水ある。猪苗代湖はまったく謎だらけなんだ」
東京でエノチャンに会ったとき、猪苗代湖の話をすると、会津若松出身の彼は即座にいうのだった。
「そこ、おれの田舎ですよ。湖底に鳥居があんです」
「湖底に鳥居か!」
なんという湖だ! 湖底に何かしらの人智を超えた秘境がある。
いつの日か、旅は湖底へと向かうのだろう。
標高3800m、アンデスのチチカカ湖には高さ200mのタキーラ・アイランドがうかんでいる。島の頂上は4000mになる。
天にうかぶその島に小舟で上陸した。
ちいさな島には黒装束のインディオが数百人くらしていた。
そこで衝撃をうけたことがあった。
島には神社はないが鳥居がみっつもあったのだ!
タキーラ・アイランドから湖畔の町プーノにもどる途上、壮大なサンセットを舟から目撃した。
その黄金の光のなかからボロボロの帆をかかげた帆船が出現した。
それは何百年の時空をこえてやってきた亡霊船のようだった。
湖上ですれちがうとき真近にみた帆船は無人だった。
猪苗代湖湖畔には上戸浜という弓なり状の砂浜がある。そこはサンセット・ビーチだった。
対岸につらなる低い山並みのむこうに陽がしずんでいく。
黄昏れの陽光が湖面にひろがってくる。
海ならば光は波で撹乱されるが湖面は鏡のようなので反射する力は強烈だ。
猪苗代湖は別名、天鏡。
陽光は溶鉱炉の火のような色あいになる。
赤々とした湖面に金色の光の道がうかびあがる。
山影に没していく太陽はさらに爆発するかのようにもえあがる。





昨日はブラックサンド・クリスタル・ビーチをたずねた。上戸浜の対岸にある。
案内人は小松書記長だ。
一昨日、書記長宅での酒宴の席でブラックサンド・クリスタル・ビーチの話がでた。
ある日、湖畔路をめぐっていたとき、偶然、黒い砂浜をみて、書記長は「砂鉄か? 」と閃きをえた。
というのも書記長は相馬の出身。そこの浜は砂鉄だ。かつて書記長が若いころは採取した砂鉄を製鉄所に売っていた。それによりたくさんの人たちが財をなした。
という記憶が、猪苗代湖の浜で書記長によみがえってきた。
それはじっさい砂鉄だった。
その話を酒宴の席で聞き、「明日、行きましょう」と、ぼくは口にしていた。
昨日は雨もようだった。磐梯山も見えない。山並みはけむっている。
スーパーで磁石を買いもとめ会津をめざし車はすすむ。
湖畔にでて途中ヨット・ハーバーをいくつか見た。海の入江のような光景だ。
書記長の記憶をたよりにブラックサンド・クリスタル・ビーチをめざすが、なかなか見つからない。
いつしか車は湖畔からはなれ山の中を走っていた。
「いや、ちがうな」
と書記長の落胆した声を聞き、先へ行く道を断念し来た道をもどっていく。
「小屋があって、そこをはいると、浜があったんだがな」
それだけが記憶。
「あっ、ここかな?」
車が脇道にはいり松林をぬけると浜にでた。
「ここだ!」
書記長が下車し磁石を手に砂地にむかう。身をかがめ磁石を砂にちかづけると、
「ついた! これはやはり、砂鉄だ!」
ぼくも黒い砂を手にすくってみる。普通の砂にはない重さを手の平に感じる。
「鉄ですね」
「間違いない」
浜はロングビーチだ。弓なり状になっている。
一画に砂にめりこむように赤茶けた岩石が散乱している。空からふってきたような有様だ。砂地から岩石を両手でかかえ引っぱりだそうと試みたがビクともしない。異様な重量だ。
「書記長! これ、隕石ですよ!」
書記長がやってきて野良仕事で鍛えあげた腕力でかかえ持ちあげようとしたが、ビクともしない。大柄の若いS君も挑戦するが、ビクともしない。S君は書生兼運転手だ。
「これは、隕石だ!」と書記長は認定した。
浜辺には砂鉄のほかに細やかな水晶や鉱石がつまったゾーンもある。
粒はマッチの火薬部ほど。地中につまってそうだ。




書記長夫妻は福島県双葉群浪江町請戸字左島塚にくらしていた。
311のその日、夫妻は用事があって町をはなれていた。津波がやってきて、町は根こそぎ波にさらわれた。およそ1800人の住民が犠牲になった。
そこは東電福島第一原子力発電所から七キロの地点。書記長夫妻は津波で家財をすべて流され、原発事故も知らされず、着の身着のままにいったんは県外に避難したが、福島にもどり猪苗代湖畔の緊急避難所や民宿らを転々としたのち新居を確保、さらに磐梯山山麓の森林脇にちいさな農地をかりうけ農業を再開した。
そのとき政府も東電も新聞も隠していたある事実を、ぼくは書記長夫妻から聞き、あまりの非道さに、怒りで体がブルブル震えてきたのだった。
この国は、根っから腐っている。
故郷の生いとなむ地を天災と人災によって追われ、流浪の民となり、しかしこの地に流れつき人生を再創造しているその夫妻は現在71歳だ。
無から、また、大地に一歩を歩みはじめた。
無とは、この地では、無常、無限の無なり。
ぼくは大きな物語に触れた気がした。
砂鉄浜を確認し、車は会津の強清水にむかった。
車中で、「砂鉄で、製鉄しよう」と書記長が提案する。
「不純物をとりのぞいてコークスで1200度ほどの火をおこしてフイゴで吹く。製造法はしらべとく」
「何、つくりますか?」
「文鎮とか」
「箸置きとか。でも、指輪もいいな」
などと談話しながら、かつて白虎隊と官軍の決戦場となった、いまもただならぬ気配を漂わせる野っ原をこえ、強清水へとひた走る。
強清水には有名な清水がある。伝説はいまにかくのようにつたえる。
ーー寛喜三年、村に木こりをしていた与曾一、与曾二という父子がいた。父の与曾一は、まじめな働き者だったが、息子の与曾二は、なまけ者で年中酒をのみ、果てはおいはぎまでするようになっていた。息子の与曾二の悪さざんまいで、米も買えないありさまだったが、どうしたわけか、父の与曾一は山仕事の帰りには、いつも酒に酔っていた。不思議に思った与曾二があとをつけてみると、岩の間からあふれる活水を飲んでいた。与曾二は、清水を酒にたとえて飲む、父の姿に、親不孝をくやみ、以後、孝養をつくしたという。今の強清水がそれだと言われている。
まずは、ひとくち飲んでみる。
それから一軒の手打ち蕎麦屋「もろはくや」にはいった。女将さんは趣味で画文を描いていて、その小作品が店内にかざってある。
座敷にあがった。
ひとつ85円のニシンとイカの天ぷら、それと名物あげ饅頭、味噌おでん、そばはもり、カップ酒を注文した。
座敷の欄干上に歴史絵があった。
内容は、古戦場、会津城の下の原野で会津藩兵士たちが、馬に乗ったり、大砲を撃ったり、演習中だ。絵に躍動感がある。
女将がやってきて、「その絵は磐田和上という有名な方が描いたもんです。磐田画伯はシルクロードをながいこと旅し大作を描いていた方で、シルクロードの大作は会津城が所蔵しています」と解説してくれる。


「女将さんは、若いころから絵を描いたりしてたんですか?」と聞くと、女将さんは言うのだった。
「あたしは若いころは砲丸投げをやってたんです!」
「えっ! 砲丸?」と書記長とぼくは同時に声をあげていた。
「そうです。砲丸です。高校時代に、あたしは3年間、インター杯で1位だったんですよ」
おもわぬ話しの展開に、ぼくらはただただおどろくばかりだった。
「砲丸か!?」と書記長はうなった。
「ど、しました?」と、ぼくは聞く。
「製鉄して、砲丸をつくる!」
「そこ、いきますか!?」
「つくろう!」
女将は、この客たちはいったい何を話してるんだ、と怪訝な顔をしている。
そのときの女将との対話で知ったのだが、ぼくらが席をとってる座敷の壁やら床の間にかざってある額縁いりの絵は、じつは煙草のフィルターやパッケージを使ったコラージュ作品だったのだ。制作者は女将だ。
「あたしの生家がタバコ屋だったもんで、これ、あたしがつくりました」
心して鑑賞すると、大変な労作だ。
しかも、モダーンだ。



もはや、数時間のあいだに、猪苗代湖マジックに幻惑されている自分がいた。
こうして、トリップ・リアリゼーション福島篇が火蓋を切った。
この旅は、いったい、どこまで行くのか?

