
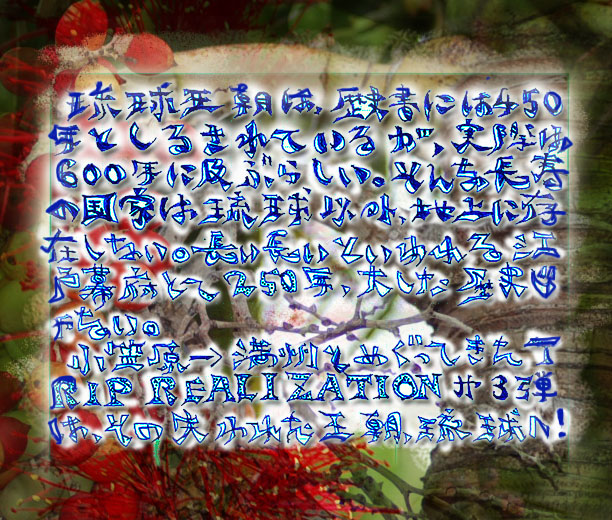
1
沖縄からもどって数日たつのに魂がぬけてしまっている気分だ。
与那国島産の泡盛〈どなん〉を飲んだ。

アルコール度60度という火焔酒だ。
それをふるまってくれた上地さんは、「強いけど喉は刺しませんよ」という。
正しい泡盛のやり方を知った。
大き目のグラスに氷をたっぷりいれ、水を七分目ほどそそぐ。そこに泡盛を並々となるまでつぐ。それでしばらく、待っていると、氷と水と泡盛がまじってくる。
それをすするように飲む。
というのがおいしく飲むレシピだが、見ていると誰もそんな悠長なことはしていない。
氷と水をぶちこみ、ずるずるすすっている。
飲みだしたら長丁場になる。6時、7時から飲みはじめて午前3時ごろまで飲んでいる。
民謡酒場にも行き、ライブ・ハウスにも行き、カラオケにも行く。
どこにも建前のような時間はない。本心をぶつけあい、酒に全身全霊ひたっている。おぼれている。
ぼくが沖縄で会った酒呑みは、みんなそんな感じだった。
なかでも上地さんは、琉球酒仙界の頭領のようだった。
上地さんは、沖縄では有名な実業家一族の代表。代々、赤サンゴの漁と加工業を独占してきた。自社が経営するホテル内スーベニア・ショップでは、上地さんが自ら彫った赤サンゴのオブジェが数百万、数千万の値がついて売られていたし、何の細工もない赤サンゴの枝は1億円の値札がついていた。

上地さんは、米軍占領下Aサインの営業許可証をもらっていた有名なステーキハウス<ステーツサイズ>のオーナーでもある。だから毎晩早い時間はレストランにいて、接客している。

モダンな柄のアロハが似合う。一見、強面のマフィアに見えるが、その人柄は漫談師のようだ。
「愉しみましょっ!愉しみまっしょ!」
を連発し、くしゃくしゃに笑う。

<ステーツサイズ>ではじめて会って、1時間ほどで意気投合した。
はじめは一夜目なので酒はひかえ目にと思っていたが、対面した途端、「もう今夜は飲んじゃえ」と、その酒がどういう酔い方になるのか見当もつかなかったが、その気になった。
それは日常の情性的な飲酒とはちがう、百年に一度の酒宴にのぞんでいるかのような、たぶん酒そのものの力だろう、無限の時空へダイブした。
その瞬間から意識がと切れ、翌朝目ざめたときには何の記憶もなかった。これほど、空白になったのはひさしぶりだった。
それは酒の性質と自分の体質がみごとに溶け合ったということだろう。
朝、ホテルに上地さんは姿を見せた。
車に乗りこむと、すぐに迎え酒ですと缶ビールがさしだされ、一口すすった。
昼近く、上地さんが経営する琉球村に到着し、貴賓室へと通された。

大卓をかこみ、すぐに村の人がお盆に泡盛、水、氷をのせてはこんできた。肴は海ぶどうにもずく酢だった。
海ぶどうはいま海でとってきたばかりに感じるほど、新鮮で潮っ気にみちていた。もずく酢も胃に安らぎをあたえてくれる。
泡盛を飲む。上地さんは水代わりに飲む。「水分をとりましょう」と、泡盛を飲む。
村内をめぐる。赤道直下級の陽がふりそそいでいる。肌が焦げる。村は山中にあり、そこは観光施設だが、施設はすべて上地さんが何十年もかけて収集したという古民家だ。

琉球文化の保存を天命にする上地さんにとって、かつて琉球の生活がいとなまれていた古民家は、用美の窮極なのだろう。

かつてぼくが仕事で関係していた『エスクァイア』のキャッチコピーは『ART OF LIVING』だった。

古民家に見る沖縄の気候を配慮したつくりは、もはやわれわれの生活感覚にはない、自然と一体化した生活の知恵にあふれていた。

風、光を感じさせる家だった。大気へとひらかれた空間だった。暮らす人の心を解放させる聖なる棲家だった。
その古民家の一軒にあがった。
畳の大広間。あぐらをくんで座ると、すぐにビールがお膳ではこばれてきた。上地さんと乾盃した。
廊下に三味線をかかえた着物姿の男性がふたりたち、弦を調律していた。その弦の音が乾いた南国の空気をエキゾチックな色に染めた。

泡盛がはこばれてきた。すでに昨夜の泡盛は発散してしまっていた。泡盛と氷と水が体にしみわたっていく。

その清涼感たるや、深い森の奥の滝のしぶきをあびているかのようだった。
家屋の外は、激烈な陽ざしがふりそそいでいるのに、家屋がつくりだす影のなかは、三味線の音を響かせ、霊妙と感じる時間が流れていた。
「時間がとまってる」

と上地さんにいうと、
「ここは特別です」
と、茶目っ気を浮かべた酔顔をむける。
「さっ、飲みまっしょ」
とグラスをぶつけあう。
日中の暑さが、酒をうまくしている。
チェイサーはビールだ。
やがて、演奏がはじまった。庭では来村者を前に芸能が披露され、上地さんは鳥の鳴き声のような指笛をならす。上地さんは鳥になってしまったのか。

そのうちあぐらを組んだまま、両手を波うたせる。手が踊っている。鳥になって宙を舞っている。
庭では琉球の民族服を着た人たちが王朝時代の式典を披露している。鑑賞者は白人も多い。バリ島を想いうかべた。金髪の少年ふたりが仲よく座っている。

やがて、ひとりの老婆が現れ、
「うめとうば」
と上地さんが声をかけると、老婆は庭から座敷にあがってくる。
「93歳の新入社員です」
と紹介してくれる。ふたりは琉球語で、世間話をしている。うめとうばの顔は、しわがない。瞳が輝いている。よく笑う。少女のようにも見える。

「うめとうばは村一番の人気者なんですよ」
「どうしたら、そんなに元気でいられるんですか?」
と、うめとうばにきくと、
「そりゃ、毎日楽しんで生きることです」
と笑う。
「わたしは何の心配もなく毎日生きています」
いうことがシンプルだ。
いま自分がいるその場所が天国の光景におもえてきた。
93歳の老婆の過去をおもえば、戦争も体験し多難であったはずだ。なのに、いま目の前にいるうめとうばには、そんな過去を微塵も感じない。
花が咲くように笑っている。
上地さんとうめとうばは、現実には村の代表と新入社員の雇用関係にある。
なのに友人同士のように語り合っている。
そこには、むきだしの人間がいる。
琉球村は人間の故郷だ。

うめとうばは庭にでていき、頭に一升瓶を立ててのせ踊っている。盆踊りだ。一升瓶は落ちない。はりついたようにうめとうばの頭上に立っている。
うめとうばは踊りの輪の中心で、ヒラヒラ両手を泳がせている。
ひと踊りすると、うめとうばはまた座敷にもどり、今度は上地さんと踊っている。
「毎日、楽しんで暮らすことです」
うめとうばは踊りながらいう。
上地さんは泡盛を飲み、指笛をならし、踊ってる。鳥になったふたりは踊っている。

この世の眺めとはとうていおもえない。
それは、やはり天国の光景だ。
63歳の上地さんと93歳のうめとうば、おのおの人生を踊りでまじえている。
そこに琉球の長い歴史を感じた。
琉球の時間が流れている。
「さっ、飲みまっしょ」
「飲みましょう」

盃をかわす。
いまここにいて生きている時間が、この世でいちばん貴重なこと。それにまさるものはない。それにまさる喜びはない。
たしかに、人を感動させる音楽や映画や文学や芸術はこの世にあるが、人と人が出会っていっときを共にすごす喜びにまさるものはない。
上地さん、うめとうばの存在そのものが琉球芸術の至高の宝だ。人こそが芸術であり、美だ。それは人を酔わす。

南国の空気をふるわせて、琉球魂がつたわってくる。泡盛の酔いとまじり、ふかく心の底へと沈んでゆく。
心によどんでいた何かが消えてゆく。
泡盛がもたらす酔いはなめらかだ。
冷たい茶がでてきた。
一口すすると、目に冴えがくる。見てる世界が鮮明になる。
「何ですか、この茶?」
「サンピン茶です」
「こんなにうまいんだ」
体にまとわっていた暑気もうせた。
涼気を感じる。中国茶ににている。何もかもすぐれている。
空気はどこまでも清潔だ。
「上等でしょ」
「何もかも、時間まで」
「上等を楽しむんです」
われわれは山道を國場邸へと歩いてむかっている。たどりつくと、あまりにさっぱりした平屋の家だった。



「さ、あがりまっしょ」
座敷にあがった。畳である。柱の数は多いが、どれも細い。明朝の家具のようだ。全体質素である。琉球王朝の様式とは異なる。
「わたしがゆずりうけ、建材を20年ほど海中に寝かしたあと、組みあげました」
「釘は使ってないですね」
「伝統工法です」
壁に髷の写真が飾ってあって、解説が書いてある。
——−國場幸太郎の父・幸直の欹髻−——
國場幸直は、その父親である幸禄とともに誇り高い人であった。幸禄は、明治十二年以降に発令された断髪令に私財を投げ打ってまで反対し、琉球士族の証しでもある“欹髻”を切らなかった。幸直もまた、九十六歳の長寿を全うするまで、” 欹髻”を貫き通した。幸直は「カンプータンメー(髷のおじいさん)」と愛称で呼ばれ、人々から愛された人物であった。
この旧宅は國場幸太郎が住んでいたようだ。生まれは1900年。すでに琉球は沖縄となっていた。
幸太郎の家は貧しく、13歳で大工の年季奉公にでた。19歳で宮古島へ渡った。その後上京し、大工としての腕をみがき、帰島。家族のために建てた家と想われる。


心地よい。家屋全体の印象は軽い。見事に直線で構成されている。
木の肌をさらしている。
しかしこの家具のなさは、むろんいま人が住んでないからだろうが、潔癖だ。
寺のようだ。でも抹香くさくはない。
無垢も感じる。
琉球菓子がでてくる。

泡盛もでてくる。
「いやぁ〜、楽しい」
上地さんの顔はほころびっぱなしだ。
帰らぬ飛行機に乗った青年にも、楽しい一日はあったのか。
いまが楽しければいいじゃないかと人は言う。しかし、いまはすぐに去る。
陰陽で、この世界が成立しているとしたら、かならず陽のあとに陰はくる。あのうめとうばの93年の人生には、歴史をふりかえれば多くの死者をだした飢餓も、戦災も、占領下もあったはずだ。そのときもうめとうばは“陽”だったのか。
1950年生まれの上地さんは、1972年の沖縄返還までのあいだ、ずっと米軍占領下にいた。
その時代の話を上地さんはしない。
上地さんは上地はジョーチとも読めるからジョージと呼んでくれ、でも、ジミーでもいいよ、という。
「じゃ、ジミーにしよう」
「モリちゃんでいい?」
「いいよ」
「楽しいな、いっしょにいると」
「うん」
「昨日、モリちゃん、泣いてたよ」
「うん。うれしくて」
「明日、別れると思うと涙でてくる」
「そうだな」
「な、帰んないでよ」
「そんなわけに行かないよ」
「そんな冷たいこといわないでよ」
ちょっとおかまチックになってきた。
市内にもどり、<ステーキサイド>でステーキを食べ、また泡盛を飲んだ。今日は、氷と水でうすめて飲んだ。
TVニュースは、瞬間最大風速が70メートルに達する台風7号が沖縄に接近していると報じている。那覇には強い風が吹いてはいるが、雨は降っていない。
カラオケ・スナックにうつり、ジミーはいう。
「モリちゃん、明日、飛行機、飛ばないよ」
「飛ばなきゃ飛ばないでいいよ」
「飛ばないよ。だから今日は朝まで飲もうよ」
「飲むよ」
「飛ばないよ。飛ばない」
ぼくは、どっちでもいいやと思っていた。
明日のことなんてわかんない。
ジミーは、「泣きそうだよ。こんなのはじめてさ。いままで、何百人、何千人かわかんないけど、本土の人、むかえて、別れが泣きたくなった、はじめてさ」と枯れきった声でいう。
「こんなのはじめてさ」
「俺だって、そうだよ」
「あのさ、<悪の十字架>ってクラブがあってさ」
「何だ、それ?」
「だからナイト・クラブよ。それでさ、行ったんだ、そこに。そしたら店があいてないのよ」
「なんで?」
「そこにホステスが出勤してきたから、聞いたのさ。なんであいてないんだって?」
「そしたら?」
「いま何時っていうのよ。時計見たら、8時だから、そういったさ。そしたら、ホステスが、あくの10時よって」
「?」
「だから、いったさ、あくの10時かって」
「なんだよ、掘ったイモいじったなってやつか?」
「何、それ?」
「ホワット・タイム・イズ・イット・ナウ、いま何時?」
那覇の夜は、矢沢永吉ソックリ・ショーのカラオケ・スナック〈タカシ〉でふけていく。マスターのタカシさんはカウンターで泥酔しているぼくらを笑いながら歌っている。
——−時間よとまれ
生命のめまいのなかで———


