
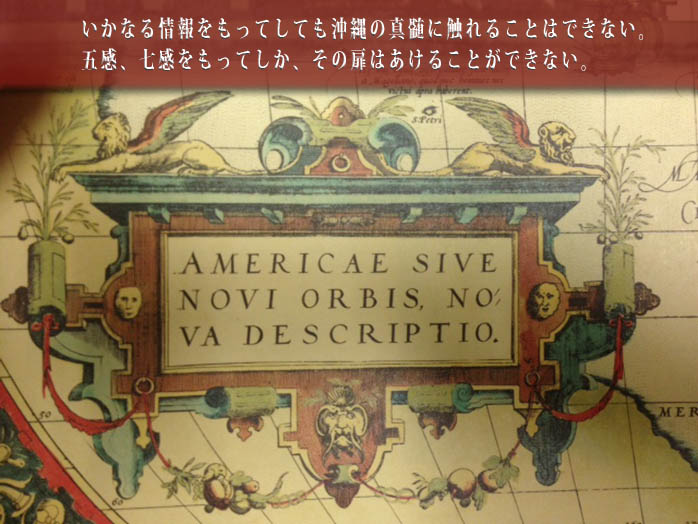
2
最後の船旅は、たぶん、小笠原。大海原を越えて行くには、片道25時間の船便しかない。2年前は3度行き、3度とも父島から母島に渡り、一度はマグロ船に乗り沖合に出漁、そのときマグロは釣れなかったが、3メートルほどの白鮫を釣りあげた。といっても、釣ったのは、元湘南のヤンキーのヨシだけどね。
ぼくは曽祖父が太平洋航路の船長だったからか、父も大学時代にボート部だったからか、海に強い。小笠原の漁師がびっくりするくらい強い。船に強い。
嵐の海でも船酔いしない。
キャロット・アイランドへ向かう船は完全に凪いだ海原を快走していた。
行く手の水平線上に皿を裏返した様な島影が浮かぶ。それが数10分後には上陸している離島だ。甲板で海を見ている。遠く水平線上に白波がたっている。
「あの白波のところが、サンゴ礁でっす」
傍のジミーが指さす。
昨日、ジミーとは那覇空港の食堂で会った。
空港食堂はジミーの一族が経営している。他に数軒、空港内に店を持っている。
空港食堂はローカル感たっぷりの大衆食堂で大人気だ。メニューはソーキそ ば、ゴーヤチャンプルー、チキアギ(さつまあげ)など、ポピュラーなものばかりだ。
空港食堂でジミーと会い、裏口を抜け3階の高級な琉球料理の店に移り、そこで腰をすえ、本格的に飲みはじめた。その店もジミーの一族の店で、空港内で一番はやっている。
ジミーと仕事の話は明後日と決めたので、真昼の空港内酒宴に勢いづいて、明日、予定もしてなかったキャロット・アイランドに行こうとなった。
酒は酔いここち、という。
酔いは心に直結している。心に直結していることは、他にも、えーと、恋、とか、熱い友情とか、大事な人の死去に接した時とか、いろいろある。
酔いここちは人が望んだ通りにはならない。心がボロボロになってしまうこともある。そんな歌も多い。ひとりで飲んでも楽しくはない。酒の席を共にするひとと、気持ちをひとつにし、陽気に時を過ごせば、酔いここちはすこぶる愉快になり、日頃決して覚えることのない高揚感にずっぽり包まれる。かなりの快楽だ。
早、空港で、そんな、 酔いここちにひたっていた。まだ、太陽は空の高いと ころでギラギラと輝いていた。
キャロット・アイランドへの船は、うるまの平敷屋港から発つ。11時の便を予定して、那覇市内をジミーの運転する車で発ったが、港に行く途中、ジミーの旧知の女性と合流することになった。島で酒を飲むつもりのジミーは、彼女に、帰りの運転をしてもらうつもりだった。しかし、ハイウェイの出口を間違え、合流のスーパーマーケットにだいぶ遅れてしまった。もう11時の船には間に合わない。
次の船は2時。時間があまったので、勝連城跡に行くことに。観光名所なんか訪ねたい気分じゃなかったが、行ってみたら、小高い丘に、いかにも要塞といった趣きで、灼熱の陽を浴びている石造りの城を遠く眺めていたら、南海の島に王朝をうちたてた中世期の王族への好奇心が沸きたってきた。



遠くに勝連城跡を見て、「万里の長城みたいですね」と第一印象を口にすると、 ジミーは、そうでっしょとうなずいた。しかし陽射しが強すぎて、丘の上まで 歩いていく気がしない。登るのは次の機会にしよう。
城は15世紀からの島の歴史を目撃してきたのに、今は黙して何も語らない。
丘の上で眠る巨人。資料館でジオラマを見ると、灰色と朱色の使い方が、今も北京に残る貴族の邸宅に似ている。城跡からは大量の中国製陶磁器が出土している。



鉄製品や貝製品や骨製品も出土している。どれも手作リの温もりを感じる。
洗練も高度さも持たない形に、逆に素朴を愛する美意識を感じるが、ただ未熟なだけか。しかし、妙に生々しいオブジェ感がある。中国製の古銭も造りが荒い。
勝連城が築かれたのは 15世紀。その時代、中国は明朝、漢民族が支配していた。海洋を越えて世界へと進出していった中国史上最大規模の大航海時代。10年ほど前、東シナ海の中国沿岸沿いに、その歴史を追った。15世紀に航海に使われていた船が泉州の博物館に展示されていて、その現物をこの目で見て、あまりの巨大さに仰天してしまった。
話は、こうだ。
シルクロードはユーラシアの内陸部だけではなく、海洋にもひらかれていた。
アラビア人たちが海のシルクロードの主役だった。中国では泉州が貿易港として栄えていた。アラビア人は航海術だけではなく造船術にも長けていた。泉州に造船所をつくった。
15世紀はじめ永楽帝の命により、泉州で大艦隊がつくられた。船は総数317艘、乗組員 27,870名という途方もない規模だった。
この大艦隊が新大陸を目指し、コロンブスより70年も先にアメリカを発見。 総督は青い目のイスラム系中国人鄭和であった。
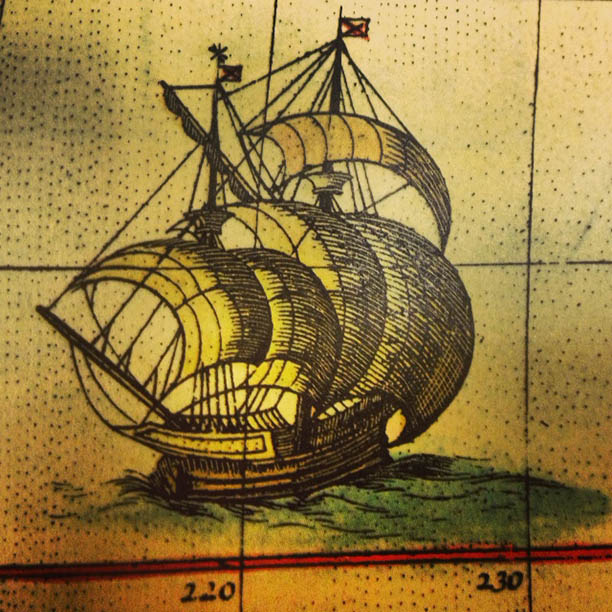
鄭和が活躍した 15 世紀には、すでに勝連城はあった。他にも琉球に城はあった。出土品から盛んに明朝と交流があったのはわかっている。東シナ海、南シナ海には、鄭和のスターウォーズ級の艦隊ばかりでなく、アラビア人もシャム人もインド人も船を操っていただろうし、当然、琉球人たちも海洋をはしりまわっていた。

世界の熱狂は、シナ海で沸騰していたのだ。地図を見れば泉州も琉球も同じ緯度だ。日本より、近い。
「世界の核心にいたんです」
とジミーに思うところを語る。
「琉球の歴史は、日本の歴史に語られているより、はるかにダイナミックだと想う」
しかし、朝から何も食べてない。タイムトリップも腹がへる。 「ジミー、腹、へったね」 「港に行く途中、マグロの刺身、安く売ってる魚屋あるんで、そこ、よってきまっしょ」 ドライバーは若い美人ママで、遊び盛りの息子ふたりを連れてきた。子どもは、 「おじさん、何やってんの?」と、興味シンシンみたいなので、「知りたい?」 と訊くと、「知りたーい」と後部座席で無垢な声がハモったので、i‐PHONE4s にいれてあるスーパーモダンロッケンロールグラフィティを再生して見せると、 ウワーっとビックリ、「こういうのつくってんだぜ」。すぐに子どもたちは、よくわかんないゲーム機に夢中になっている。
のどかなドライブだ。
人影を見ない乾いた街を走り、魚屋に到着。商店は徳永鮮魚店。冷蔵用のガラスケースに目当てのマグロはなく、ジミーがコレも上等な味ですという白身魚の刺身を買った。鯛の一種らしい。

坂を下り、港に着く。待合所で、オリオン・ビールを飲む。肴は、刺身。醤油にワサビに酢。歯ごたえもあって、ジミーの言うとおり鯛の風味だ。

南の、離島に渡るちいさな港の待合所は、空気が弛緩しきっている。音は、旧式のテレビから高校野球中継が流れてくる。気に留まるものが何ひとつない。それで神経は、どこまでも安らぐ。場が無心。こういう場は、創ろうと思ったって、できるもんじゃない。それは、それで、ある境地さえ感じる。ようは、誰も何も考えてないんだ。

海を渡り2時30分にはキャロット・アイランドに着いた。上陸すると、ロケ ットの発射台のようなタワーが立っていた。か、海底油田でも採掘してるのか。迎えのワゴン車に乗り古い集落を抜け海辺の宿に着いた。宿は少し高台にあり、 テラスが海へとせり出している。そこに、天幕を張った休息所がある。ラフな造りが、ものすごい風情をうみだしている。これも、創ろうと思ったって、創れるもんじゃない。履きに履き込んだヴィンテージの501みたいなものかもしれない。


海の向こうは本島だ。
真夏の積乱雲が本島全体にかかっている。それより高く、薄くクリスタル状の雲がひろがっている。積乱雲の一カ所に帯状の青い影が見える。ジミーが、そこを指さす。
「あそこ、雨、降ってます」
雲は一ミリも動かない。
無風だ。
「さ、裸に、なりまっしょ」

アロハを脱ぐ。天幕の下のテーブル席に着く。水をはり氷をうかべた金盥に缶ビールが冷やしてある。島に渡る前に、ジミーがお膳立てしてたんだろう。
他に泡盛。宿から、おばさんが皿や貝殻に盛ったソーキやシーフードを運んでくる。まったく何の気取りもない。貝は、目の先の海で獲れる。それをすぐ捌いて貝殻に盛る。野趣味たっぷり。貝は、東京の寿司屋だと高級ネタとして、べらぼうに高値になるらしい。



「あそこの岩礁のとこに、古酒を寝かしてあるんです」
「海底に?」
「海底に、何年も、何十年もしずめておくんです」
昨日、空港から那覇市内のステーツサイズへ流れた。酔って見る街は、たま らなくエキゾチックだ。ウルトラマンのビル。円谷プロに、確か、沖縄出身の 奇才がいたはずだ。オスプレイ 9 機が米軍基地に向かってきている。那覇市内 の裏通り。追憶。郷愁。ステーツサイズの店内。アメリカにも詩情はあった。

ミッドセンチュリーの残影。ジュークボックス。ステーツサイズの時間。また泡盛を飲んだ。




「地下、見ますっか?」
酒蔵になっているとジミーは言う。厨房の奥に、地下室への入口があり、薄暗い階段をおりていった。
「身内以外、誰もいれないんでっす」
船底のような空間に無数の甕と瓶。ひと甕、ひと瓶、数十万円、数百万円。 10 年、20 年、海底に寝かしておく。そうすると、泡盛は夢を見る、とジミーが 言ったわけではないが、たぶん。

人を酔わせて別天地へと連れていってくれる酒の精。海底で長い眠りにつく酒の精は、たくさんの夢を見て、芳醇となる。
泡盛は、キャロット・アイランドの岩礁域にしずめてある。ジミーは、その島の地主だ。
天幕の下で、泡盛を飲んでいる。
「もう、ひとつビーチ、行きまっしょ」
ワゴン車で、向った。島特産のニンジン畑を走りブッシュの小径を抜けビーチに着いた。海では、島の若者か、銛を使ってなにかをついていたが、すぐ浜に上がって、何処かに消えたので、海も浜も無人になった。
「さ、あそこのアダンの木の下にすわりまっしょ」
木陰に腰を下ろした。
すると、おやっ、風を感じる。

影の中に風がそよいでる。その風は、やさしく、体の火照りを吹き消した。
この世でもっとも快適な土地は、「永遠の五月」と讃えられるバハマであるとい われていた。年間通し気温は 15、6 度、快感を呼ぶ涼風が小さな島に吹き渡る。 しかし、バハマは、俗悪な観光地に堕ちていった。
いま、自分はキャロット・アイランドの無人のビーチにいて、アダンの木陰で 至福を、風に感じている。
「至福です」
「そう、でっしょ。これが琉球のこころです」 「真髄に触れている気がする」
「このビーチ、さしあげます」 「エッ!?」

「今日から、morinaga beach です」
アダンの木陰で、水平線を見ている。
「あそこがサンゴ礁です」
と、ジミーは遠くの白波を指さす。
われわれが「時間」と呼んでいるものの中に、「神」は存在する。
そこには宗教のように、いかなる像も形式も制度も聖典も教祖も印しも言葉もない。ただ風だけが流れている。
ジミーからもらったのは、そんな「時間」だった。
本島に戻り、夜、那覇の山羊料理屋の山海に行った。高円宮が若いころ贔屓にしていた店だ。
主人は、ジミーの同級生。座敷にあがり、山羊肉の刺身を食べる。新鮮な羊肉ほどしか、匂わない。しかも、山羊肉は、かなり美味だ。

亡くなった婆のサンシンを孫娘が弾いている。
ジミーが突然肩をぶるぶる震わす。
「ジミー、どしたんだよ」
声に、ならない。な、どしたんだよ......。
「モリちゃん、じゃん拳、やりまっしょ」
「いいよ」
「最初はグー、じゃん拳、ポン!」
2 回続けて勝った。 「こころ、読まれてる!」
また、ジミーは肩をぶるぶる震わせた。


